熟年離婚とは?原因やメリット・デメリット、手続きなどを解説

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
厚生労働省は、令和5年人口動態統計で「同居期間20年以上の夫婦が離婚した件数は39,812組であった」と公表しています。この、いわゆる“熟年離婚”は、昭和25年以降上昇傾向にあり、全離婚件数の約2割を占めるなど、社会現象として注目されています。
本記事は、熟年離婚を検討されている方や相手から熟年離婚の申し出を受けた方に向けて、熟年離婚のメリットやデメリットなどを詳しく解説していきます。熟年離婚の原因となる理由や熟年離婚で後悔しないための準備についても詳しく解説していきますので、ぜひご参考になさってください。
まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います
離婚問題ご相談予約受付来所相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。
※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
お電話でのご相談受付
0120-979-164
24時間予約受付・年中無休・通話無料
メールでのご相談受付
メールで相談するこの記事の目次
熟年離婚とは
熟年離婚とは、一般的に婚姻関係を20年以上継続してきた夫婦が離婚することをいいます。
離婚する際には、夫婦が婚姻中に築いた財産や生活に関する条件を整理し、取り決める必要があります。条件には、次のような項目が挙げられます。
- 慰謝料
- 婚姻費用
- 財産分与
- 年金分割
- 親権
- 養育費
- 面会交流 など
熟年離婚の場合は、長期間の婚姻期間を経て離婚するため、「財産分与」や「年金分割」などの金銭に関する条件で揉めやすい傾向にあります。
子供のいる夫婦の場合は、子供に関する条件を取り決める必要がありますが、熟年離婚の多くは既に子供が自立したタイミングで行われます。そのため、熟年離婚の際に子供に関する条件で争うケースはあまりありません。
熟年離婚の原因・理由は?
熟年離婚の主な原因には、次のような理由が挙げられます。
- 一緒にいることがストレス
- 価値観の違い
- 借金、浪費癖がある
- 浮気やDV・モラハラがあった
- 義両親の介護をしたくない
- 家事や子育てに全く協力してくれなかった
- 子供が自立した
上記の理由で、長年寄り添った配偶者との離婚を検討・決意される方は多くいらっしゃいます。なかには、配偶者に対する不満を長年抱え続けてきた方もいらっしゃるでしょう。
次項では、それぞれの理由についてもう少し深く掘り下げていきます。
一緒にいることがストレス

熟年離婚する夫婦は「定年退職」を迎える年齢になっている方が多いかと思います。
定年退職してからは、働いていたときの生活から一変して、仕事に出かけていた時間に家に居るようになり、毎日夫婦で過ごす時間が長くなります。家にいても家事をしないどころか、家事の負担が増えて不満に思うケースがよくあります。
過ごす時間が長くなる分、夫婦の会話もなくなり、一緒の空間にいるのがストレスとなり、離婚を考えるという方が多いようです。
価値観の違い
何十年もの間結婚生活を送る相手との価値観の違い(性格の不一致)は、大きなストレスになります。
最初は小さなストレスでも、共に過ごす時間が長くなるにつれて大きくなり、気付いたときには一緒にいるだけで苦痛を感じるようになります。価値観の違いには、「金銭感覚のズレ」や「子供に対する考え」「大切に思うものの違い」などが挙げられます。
子供のいる夫婦の場合は、子育てが終わり夫婦で過ごす時間が増えたことで相手との価値観の違いが浮き彫りになります。子供が自立したタイミングであるため、離婚を決断しやすいでしょう。
性格の不一致による離婚について、詳しくは以下のページをご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
借金、浪費癖がある
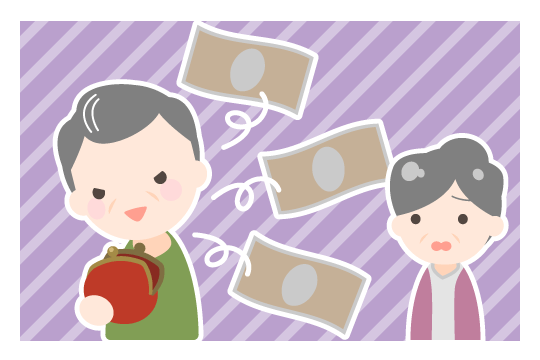
本来であれば、定年を迎える時期になり、退職金や年金がある程度確保できて、子育てや住宅ローンの支払いが終わりを迎え、悠々自適な生活を送れる老後を思い描いていたでしょう。
しかし、相手がギャンブルや趣味の買い物などで借金を繰り返しているのが発覚したり、普段から浪費癖があったりして長年耐えていた場合は、定年退職をして安定した収入が得られなくなってしまうと、将来の老後は不安しかありません。
相手の借金や浪費癖などお金に関する問題は離婚の大きなきっかけとなっています。
浮気やDV・モラハラがあった
度重なる浮気や、長年のDVやモラハラを受け続け、“子供が大きくなるまでは…”と子供の気持ちや経済的な事情を考えて、我慢していたという方は多く見受けられます。
子供が自立したことや、子供や周りからの助言がきっかけで、熟年離婚を決意するケースはよくあります。
さらに、浮気やDV・モラハラが離婚原因の場合は慰謝料を請求できる可能性もあります。
DV加害者と離婚する方法とモラハラについては、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
義両親の介護をしたくない
熟年離婚する夫婦は、両親の介護が必要になる年代であることが多いかと思います。
介護するには体力が必要ですし、心への負担もかかります。実の両親の介護ならまだしも、配偶者の両親(義両親)の介護はしたくないという方もいるでしょう。
また、義両親の介護に対し、配偶者が全く協力してくれなかったり、ねぎらいの言葉がなかったりすると、不満は募っていきます。こうして、義両親の介護が原因となり、熟年離婚に至る場合もあります。
家事や子育てに全く協力してくれなかった
特に妻が熟年離婚を決意する理由として多いのが、「夫が家事や子育てに全く協力してくれなかったから」というものです。
いまだに、「家事や子育ては女がするもの」という考えを持つ男性はいます。たとえ妻が専業主婦だったとしても、夫婦には協力義務があります。
夫が家事や子育てに全く協力してくれなければ、「なぜ自分だけがこんなにもがんばっているのか?」と不公平に感じるでしょう。こうした日頃のストレスが積み重なっていき、妻から夫に熟年離婚を切り出すことがあります。
子供が自立した
離婚が頭をよぎっても子供がまだ幼い場合、これから先のことを考えると、子供の心に与える影響や学費等が心配になり、離婚に踏み切れない方もいます。
特にこのようなケースでは、子供が大きくなり、自立したタイミングで熟年離婚を切り出すパターンが多いです。
子供が自分自身で生活できるようになったことで、離婚をためらう必要がなくなり、「もう別れてもいいだろう」と決心がつきやすくなるのだと思われます。
熟年離婚のメリット
熟年離婚のメリットには、以下のような点が挙げられます。
<熟年離婚の主なメリット>
- 日々の不満やストレスから解放される
配偶者だけでなく、配偶者の親族との関係に長年悩み耐えていた方は、熟年離婚によりその悩みを払拭できます。 - 配偶者やその親族と接する必要がなくなる
離婚後は、配偶者や親族と接する必要が無くなるため、生き生きとした生活が送れます。 - 習い事や外出など、自由な生活を送れる
離婚後は、趣味や習い事に打ち込んだり、新たな人間関係を築いたりと、今まで家族のために費やしていた時間も自分自身のために費やすことができます。
自分のペースで、自分の好きなように残りの人生を歩める点は、熟年離婚の最大のメリットといえます。
熟年離婚のデメリット
一方で、熟年離婚のデメリットには、以下のような点が挙げられます。
<熟年離婚の主なデメリット>
- 孤独を感じるようになる
離婚すると一人になるため、最初は自由で楽しくても次第に孤独を感じるようになる場合があります。 - 経済的な不安を抱く
特に専業主婦(主夫)だった方やパートタイムでしか働いていなかった方は、経済的な不安を抱きやすいです。就職活動をしても、長年のブランク期間や年齢で仕事が制限され、生活が困窮する可能性があります。 - 家事に問題が生じる
料理の作り方や掃除の仕方が分からず、離婚後に家事問題が生じる場合があります。家事問題は特に男性に生じやすい問題です。
自分の好きなように残りの人生を歩める一方で、経済的な不安や孤独などが重くのしかかり、離婚を後悔してしまうケースも少なくありません。
まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います
離婚問題ご相談予約受付来所相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。
※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
お電話でのご相談受付
0120-979-164
24時間予約受付・年中無休・通話無料
メールでのご相談受付
メールで相談する熟年離婚で後悔しないための準備
何の準備もせずに熟年離婚を進めると、不利な条件で離婚することになってしまったり、離婚後に後悔してしまったりするケースもあります。熟年離婚すると決めたら、少なくとも次のような準備は必ず行うようにしましょう。
①離婚後の住まいを決める
夫婦で購入したマイホームは離婚後どちらが住み続けるのか、離婚を機にマイホームは売却するのか、夫婦で住んでいる賃貸物件は離婚後引き払うのか、などを事前に考えておきましょう。
新しい住居に住む場合は、物件探しと引っ越し費用、住宅にまつわる初期費用などの準備をしなければいけません。
自分の条件に合う物件はすぐに見つからない可能性があるので、事前にしっかり準備しておきましょう。
②財産分与を把握する
財産分与は、熟年離婚でなくても争われやすい条件で、対象となる財産分与の把握が重要となります。
財産分与とは、「婚姻中に夫婦が協力して築き上げた財産を離婚時に分け合う行為」です。
どちらの名義であるかは関係なく、財産分与の割合は夫婦の貢献度に応じて基本的に2分の1とされています。熟年離婚の場合は、婚姻期間が長いために財産が増え、種類も複雑になっているケースが多いことから、離婚時に揉めやすい傾向にあります。
また、財産分与は「退職金」も対象となる可能性がありますが、基本的には夫婦の一方が専業主婦(主夫)であっても、分け合う割合は2分の1です。財産分与を公平にかつ離婚を後悔しないようにするには、対象となる財産分与を把握してきちんと分け合う必要があります。
熟年離婚の財産分与について、さらに詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
③年金分割の手続きを確認する
「年金分割」とは、婚姻期間中に納付した厚生年金(※かつての共済年金も含む)保険料の納付記録を、夫婦間で分ける制度です。
分割の割合は、最大で2分の1とされています。年金分割を受けた側は、自身が年金を受給することになったとき、受け取る年金額が増えます。
また、専業主婦(主夫)の多くは、「第3号被保険者」に該当しているでしょう。第3号被保険者とは、厚生年金(共済年金)に加入している配偶者によって扶養されている者のことです(※年齢や年収の条件あり)。
通常、年金分割をするには、夫婦間の合意や裁判所の手続きが必要になりますが、第3号被保険者の場合、平成20年4月1日以降の保険料納付記録については、夫婦間の合意や裁判所の手続きはなくとも、当然に2分の1ずつ分割することができます。
年金分割の詳しい内容は、下記の記事をご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
④浮気やDV・モラハラの証拠を集める
相手の浮気やDV・モラハラなどが理由で熟年離婚する場合は、精神的苦痛に対する補償として慰謝料を請求できる可能性があります。ただし、慰謝料の請求には、浮気やDV・モラハラの事実を裏付ける客観的証拠が必要です。
<客観的証拠の具体例>
- 録音データ
- 写真やメールの履歴
- DVやモラハラの内容を記録した日記
- DVによる怪我の診断書 など
このような証拠を十分に揃えることができれば、慰謝料だけでなく他の離婚条件の取り決めを有利に進められる可能性が高まります。適切な慰謝料や納得のいく条件で離婚するには、相手の不法行為を裏付ける証拠の収集が大切です。
DVやモラハラの証拠の集め方について、詳しくは以下のページをご覧ください。
熟年離婚で請求できる慰謝料はいくら?
離婚慰謝料の金額は、100万~300万円が一般的な相場といわれています。
ただし、相手の行為の内容や程度、婚姻期間の長さ、年齢、子供の有無など、個別の事情によって慰謝料の金額は異なってきます。判断に悩まれたときは、弁護士にご相談ください。
下記の記事では、離婚慰謝料の相場について詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。
合わせて読みたい関連記事
熟年離婚のベストなタイミングは?
熟年離婚のベストなタイミングは、夫婦の状況によって異なりますが、「夫の定年退職後」は良いタイミングの一つといえます。
退職時には退職金を受け取れる例がありますが、退職金は勤続年数などにより高額になりやすく、財産分与の対象です。そのため、配偶者が定年退職するまで待ち、勤め先から退職金が支払われたのを確認してから離婚を切り出すなど、計画的な熟年離婚をする方も多くいらっしゃいます。対象となる財産分与が増えれば、それだけ離婚後に手にするお金が増えるため、経済的な不安の軽減に大きくつながります。
熟年離婚の手続きの流れ
熟年離婚の手続きは、通常の離婚と同じように以下の流れで進めていきます。
- 協議離婚を行う
- 離婚調停を申し立てる
- 離婚裁判を申し立てる
離婚を成立させる方法は、主に上記の3つです。
まずは、夫婦が話し合いで離婚を成立させる協議離婚からスタートするのが一般的です。
次項では、熟年離婚における各方法について詳しく解説していきます。
主な離婚の方法(協議離婚・離婚調停・審判離婚・離婚裁判)の概要は、下記の記事をご参照ください。
合わせて読みたい関連記事
協議離婚を行う
協議離婚とは、「夫婦が話し合いで離婚を成立させる離婚方法の一つ」です。
まずは、相手に離婚したい旨を伝え、相手がそれに合意した場合は、離婚条件の取り決めを行います。
離婚条件には、財産分与や年金分割、相手の不法行為が認められる場合には慰謝料などが含まれます。離婚条件を取り決める際は、「言った言わない」の水掛け論となりやすく、争いへと発展する可能性が高いです。そのため、取り決めた離婚条件は離婚協議書を作成して公正証書化するなどの対策が必要です。
協議離婚の進め方や注意点については、以下のページをご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
離婚調停を申し立てる
離婚調停とは、「家庭裁判所の裁判官や調停委員を介して夫婦が話し合いで離婚を成立させる離婚方法」です。婚姻期間が長期に及んでいる熟年離婚は、財産分与や年金分割などの離婚条件で揉めて離婚調停を利用する夫婦が多い傾向にあります。
離婚調停は、調停委員が夫婦双方から個別に意見を聴取して話し合いを進めていくため、夫婦は直接顔を合わせずに済みます。そのため、感情的になりにくく、話し合いをスムーズに進められます。
離婚調停の基礎知識については、以下のページをご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
離婚裁判を申し立てる
離婚裁判とは、「夫婦が話し合いで離婚を成立できない場合に、裁判所の判断で強制的に離婚を成立させる離婚方法」です。日本では、離婚調停を経ていないと離婚裁判を申し立てられない(調停前置主義)ルールがあります。そのため、離婚裁判は、いわば離婚を成立させるための“最終手段”です。
離婚裁判では、裁判で離婚が認められる理由=「法定離婚事由」がなければ裁判官から離婚を認めてもらえません。法定離婚事由には、以下の5つが挙げられます。
- ① 不貞行為
- ② 悪意の遺棄
- ③ 3年以上の生死不明
- ④ 回復の見込みがない強度の精神病
- ⑤ その他婚姻を継続し難い重大な事由
離婚裁判の流れや費用などについては、以下のページをご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
熟年離婚の子供への影響や養育費はどうなる?
子供が既に自立していたとしても、以下のようなケースでは、熟年離婚によって子供に負担をかけてしまう可能性があります。
- 離婚により親の生活が苦しくなり、子供が親に経済的援助を行わなければならないケース
- 本来なら夫婦間で介護を行うところを子供に頼らなければならないケース
また、養育費については、20歳まで支払われるのが一般的ですが、未成年に対してではなく、「経済的に自立できていない子供(未成熟子)」に対しても支払われます。そのため、子供が経済的に自立していなければ養育費を支払う必要があります。
ただし、養育費の支払期間は夫婦で話し合って決められるため、お互いに合意できれば、支払期間を自由に決められます。
離婚後の養育費について、詳しくは以下のページをご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
熟年離婚に関するQ&A
- Q:
-
熟年離婚をする場合、その後の生活費を相手に請求できますか?
- A:
-
熟年離婚後の生活費は、元配偶者に請求することはできません。
婚姻中であれば、一般的に収入の多い方が少ない方に対し、生活費として「婚姻費用」を支払う義務を負います。しかし、離婚が成立すると、夫婦からいわば赤の他人となり、婚姻費用を支払う義務はなくなります。そのため、相手が任意で応じてくれない限り、熟年離婚後の生活費をもらうことはできません。
ただ、夫婦間の収入差などを踏まえ、離婚する際の「財産分与」や「慰謝料」のなかで、離婚後の生活費を考慮して金額が調整される場合はあります。
- Q:
-
熟年離婚後に遺族年金を受け取ることは可能ですか?
- A:
-
熟年離婚後に元配偶者が亡くなったとしても、遺族年金を受け取ることはできません。
すでに婚姻関係は解消されているためです。また、配偶者が亡くなった時にはまだ離婚が成立する前だったという場合でも、再婚すると遺族年金は受け取れなくなります。
一方で、元配偶者との間に生まれた子供が次の2つの条件を満たしている場合は、遺族年金を受け取れる可能性があります。
- 子供自身の年齢が18歳になった年の年度末まで
もしくは20歳未満で障害等級1級または2級の障害があるとき - 子供自身が「元配偶者によって生計を維持されていた」ことが証明できるとき
しかし、亡くなった元配偶者から養育費を一切受け取らずに子供を育てている場合や子供がすでに成人している場合、元配偶者が再婚していた場合などは子供も遺族年金は受給できません。
- 子供自身の年齢が18歳になった年の年度末まで
熟年離婚で後悔しないためにも弁護士にご相談ください
結婚生活が長かった分、離婚後の生活や経済的事情で悩んだり、財産分与が複雑になったりすることもあり、熟年離婚は思っているよりも大変です。
「別れなければよかった…」と後悔してしまう事態を避けるためには、離婚時に請求するお金で当面の生活費をどのくらい確保できるか確かめる、離婚後の住まいを探して目星をつけておくといった、事前の準備が重要です。
ご不安な方は、ぜひ弁護士にご相談ください。ご相談者様のお話を丁寧に伺い、どんなことに注意すべきか、事前にどのような準備をしておいた方がいいか等、適切に判断してアドバイスいたします。また、相手との交渉や裁判所での手続きを引き受けることも可能です。
熟年離婚を考えたら、焦って行動に移すのではなく、まずは弁護士に相談して慎重に進めていきましょう。
まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

- 監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
- 保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)
弁護士法人ALG&Associates 事務所情報
お近くの事務所にご来所いただいての法律相談は30分無料です。お気軽にお問い合せください。
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。
- 関連記事















