協議離婚|進め方や注意点、話し合うべき内容など

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
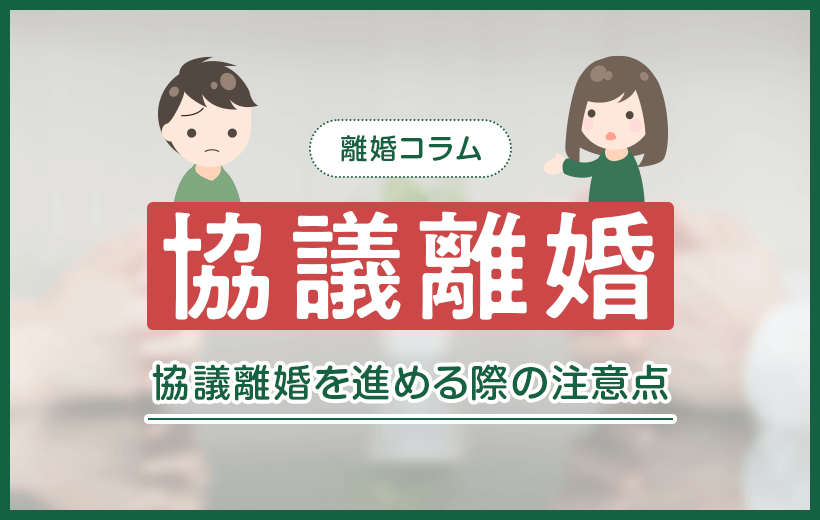
協議離婚は、夫婦の話し合いによって離婚を成立させる方法です。手間や費用がかからないため、日本では離婚する夫婦の大半が協議離婚を選択しています。
ただし、協議離婚では取り決める事項が多く、抜け漏れがあると離婚後にトラブルになったり、生活に支障が出たりする可能性があるため注意が必要です。
本記事では、協議離婚のポイントや他の離婚方法との違い、取り決めるべき内容などを詳しく解説していきます。離婚を検討中の方は、ぜひご覧ください。
まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います
離婚問題ご相談予約受付来所相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。
※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
お電話でのご相談受付
0078-6009-3006
24時間予約受付・年中無休・通話無料
メールでのご相談受付
メールで相談するこの記事の目次
【動画で解説】協議離婚|話し合いの際の注意点や決めるべき内容などの基礎知識
協議離婚とは
協議離婚とは、裁判所の手続きを利用せず、夫婦で話し合って離婚する方法のことです。役所に「離婚届」を提出し、受理されたら離婚成立となります。夫婦の合意さえあればいいので、離婚理由は問われません。
離婚方法のうち、最も多いのがこの「協議離婚」です。令和5年の調査では、離婚した夫婦の約90%が協議離婚を選択しています。
なお、話し合いがまとまらない場合は「離婚調停」を利用するのが一般的です。
協議離婚と離婚調停の違いは、「誰が話し合いに参加するか」という点です。協議離婚は夫婦だけで話し合うのに対し、離婚調停は調停委員という第三者を挟んで話し合います。
また、調停にかかる期間は平均「半年~1年以内」と、比較的短くなっています。ただし、調停も“話し合い”の場なので、最終的に夫婦の合意がなければ離婚は成立しません。
それぞれのメリット・デメリットは、下表をご覧ください。
| 協議離婚 | 調停離婚 | |
|---|---|---|
| メリット |
|
|
| デメリット |
|
|
調停でも合意できない場合、「離婚裁判」を提起して、相手と争うことになります。
離婚裁判とは、夫婦が合意できないとき、裁判所が離婚の可否を決定する方法です。裁判所が離婚を認める旨の判決を下せば、晴れて離婚が成立します。
ただし、離婚裁判は終結まで「1~2年」かかるケースが多く、準備に手間もかかります。
早めに離婚を成立させたい方は、協議離婚での解決を目指すのがおすすめです。
協議離婚にかかる期間
協議離婚が成立するまでの期間は、「数ヶ月~1年」というケースが多いです。
もっとも夫婦の合意さえあれば良いので、最短1日で離婚を成立させることも可能です。例えば以下のようなケースでは、早期の解決が見込めるでしょう。
- 夫婦が離婚に合意している
- 離婚条件に争いがない
- 子供がいない
一方以下のようなケースでは、離婚成立まで1年以上かかることもあります。
- 相手が話し合いに応じない
- 財産分与が複雑
- 親権でもめている
協議離婚の進め方とポイント
協議離婚を目指す場合、まずは相手に「離婚したい」と切り出さなければなりません。直接言いづらいという方は、電話やメール、LINE、手紙などで伝えても良いでしょう。
相手と合意できたら役所に離婚届を提出し、受理されれば離婚が成立します。
協議離婚を進める際のポイントは、以下の3つです。
- ①離婚条件もきちんと話し合う
離婚時は、財産分与や親権などの離婚条件も取り決める必要があります。漏れがあると、離婚後の生活に影響が出かねないため注意しましょう。 - ②合意内容は書面に残す
言った・言わないのトラブルを防ぐため、合意内容は「離婚協議書」などの書面に残しましょう。 - ③離婚協議書は「公正証書」に残す
公証人が作成する公正証書は、証拠能力が非常に高い“公文書”ですので、離婚後のトラブルを防ぐのに効果的です。
詳しくは以下のページをご覧ください
合わせて読みたい関連記事
離婚協議書は公正証書で作成する
公正証書とは、公証人が作成する“公文書”のことです。離婚の場合、財産分与や慰謝料、親権といった離婚条件について、合意内容を公正証書に残すのが一般的です。
立会人がいない協議離婚では、離婚後に相手とトラブルになることも珍しくありません。「そんな約束はしていない」「養育費の金額が違う」などと言われ、当初の約束が果たされない可能性があります。
公正証書を作成すれば、公証人という第三者が介入するため、相手が言い逃れするのは非常に困難です。また、公正証書の原本は公証役場で「20年間」保管されるため、紛失の心配もありません。
さらに、公正証書に「強制執行認諾文言」を入れておくと、金銭の支払いなど一定の内容の取決めについては、相手が約束を守らない場合、裁判手続きを経ることなく強制執行を行い、財産を差し押さえることができます。
協議が長引きそうなら離婚届不受理申出をする
「離婚届不受理申出」をしておけば、知らぬ間に相手が離婚届を出してしまっても、受理されるのを防ぐことができます。
協議離婚は、役所で離婚届が受理されれば成立しますが、役所は「夫婦の合意があるか」までは確認しません。そのため、こちらが離婚に同意していないにもかかわらず、相手が勝手に離婚届を作成・提出してしまうケースもあります。
一度離婚届が受理されると、離婚を取り消すには裁判所の手続きを踏まなければならないため、事前に不受理申出をしておくと安心です。
「離婚届不受理申出」の方法や注意点は、以下のページで解説しています。
合わせて読みたい関連記事
協議離婚で話し合うべき内容
離婚時は、以下の「離婚条件」についてもしっかり取り決める必要があります。
- 慰謝料
- 財産分与
- 年金分割
- 親権
- 養育費
- 面会交流
このうち「親権」以外は離婚後に取り決めることも可能ですが、離婚後に相手が話し合いに応じてくれるとは限りません。そのため、離婚条件はすべて離婚時に取り決めるのが基本です。
それぞれの項目について、詳しく解説していきます。
慰謝料
相手の不倫やDV、モラハラなどが原因で離婚する場合、精神的苦痛を負ったとして「慰謝料」を請求することができます。
協議離婚の場合、相手の同意があれば慰謝料を支払ってもらうことができますし、金額も自由です。
しかし、不倫やDVの証拠がないと「お前の勘違いだ」「支払う義務はない」などと言い逃れされ、支払いを拒否される可能性が高いでしょう。そのため、相手の行為を裏付ける証拠を集めることが重要となります。
おひとりで証拠を集めるのが難しいときは、探偵に依頼するという方法もあります。弁護士法人ALGでは、グループ会社であるALG探偵社と連携を取って、慰謝料請求を進めていくことが可能です。
詳しくは以下のサイトをご参照ください。
財産分与
財産分与とは、婚姻期間中に夫婦が協力して築きあげた財産を、離婚時に分け合う手続きです。
それぞれが公平に受け取れるよう、財産は基本的に2分の1ずつ分け合います。よって、財産の名義や収入の金額差などに関係なく、夫婦で平等に分け合うのが基本です。
財産分与の対象となるのは、以下のようなものです。
- 預貯金
- 不動産(土地・建物)
- 自動車
- 有価証券
- 保険解約返戻金
- 退職金 など
一方、独身時代に貯めたお金や、親族からの生前贈与や遺産相続によって得た財産は、財産分与の対象外となります。
合わせて読みたい関連記事
年金分割
年金分割とは、婚姻期間中に夫婦それぞれが納めた厚生年金を、離婚時に分け合う制度です。
専業主婦や収入が少ない方は、離婚すると将来の年金額が大幅に減ってしまい、生活が苦しくなるおそれがあります。
そこで、年金分割によって相手が納めた厚生年金の一部をもらい、将来受け取る年金に上乗せするのが本制度の目的です。
なお、「単に将来受け取る年金額を分割できるわけではない」という点には留意する必要があります。
年金分割の種類や方法については、以下のページで解説しています。
合わせて読みたい関連記事
親権
未成年の子供がいる場合、離婚時に親権について取り決める必要があります。通常、親権を持つ「親権者」が子供を引き取り、育てていくことになります。
離婚届には親権者について記載する欄があり、未成年の子供がいるのにこの欄が空白になっていると、役所は受理しません。つまり、親権は協議離婚する際に必須の条件ということです。
ただし、親権は特に揉めやすいため、ポイントを押さえたうえで協議するのが良いでしょう。詳しくは以下のページをご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
養育費
離婚後に子供と一緒に暮らす親は、もう一方に「養育費」を請求することができます。
養育費は子供の生活に必要なお金のことで、食費や衣服代、教育費などが含まれます。
離婚して子供と離れて暮らすことになっても、親であることに変わりないため、子供が自立するまではしっかり支援すべきとされています。そのため、養育費を請求された側は基本的に拒否できず、取り決めた額を支払うことが義務付けられています。
養育費で決めるべきなのは、以下のような項目です。
- 金額
- 支払方法
- 支払日
- 支払期間(例:子供が20歳になるまで)
養育費を取り決める際のポイントは、以下のページで解説しています。
合わせて読みたい関連記事
面会交流
面会交流とは、離婚後に子供と離れて暮らす親が、子供と直接会って遊んだり、電話やメール、手紙を通して交流したりすることをいいます。
面会交流は「子供が親と触れ合う権利」なので、親の感情や都合を理由に拒否することができるとは限りません。また、子供に負担がかからないよう、子供の年齢や生活リズム、生活環境などを考慮したうえで条件を決める必要があります。
面会交流で取り決めるべきなのは、以下のような項目です。
- 頻度
- 時間
- 場所
- 連絡方法
- 子供との待ち合わせ方法・場所
- 学校や習い事の行事への参加の有無
- プレゼントの可否 など
面会交流を決める際のポイントは、以下のページで解説しています。
合わせて読みたい関連記事
協議離婚の話し合いがまとまらない場合の対処法
協議離婚はお互いの同意が必要なので、意見が食い違うといつまでも離婚は成立しません。また、話し合いが続くとお互いが感情的になり、話し合いが進まないおそれもあります。
そこで、話し合いがまとまらない時は以下の対応も検討すると良いでしょう。
- 別居を検討する
- 弁護士に相談する
それぞれのポイントを詳しく解説していきます。
別居を検討する
別居することでお互いが冷静になり、話し合いがスムーズに進む可能性があります。
また別居期間があると、裁判で離婚が認められやすくなります。
通常、裁判で離婚を争う場合、「民法上の離婚理由(法定離婚事由)」がないと離婚は認められません。
別居によって「夫婦関係が破綻している」と判断されれば、離婚事由を満たすとして、裁判所に離婚を認められる可能性が高くなります。なお、必要な別居期間は「3~5年」が目安とされています。
「別居後の生活費が不安」という方は、お互いの収入次第で相手に「婚姻費用」を請求できる可能性があります。専業主婦や収入が少ない方は、婚姻費用も忘れずに請求するようにしましょう。
別居する際のポイントや注意点は、以下のページで解説しています。
合わせて読みたい関連記事
弁護士に相談する
弁護士は離婚の進め方を熟知しているため、自分で行うよりもスピーディーに、また有利な条件で離婚できる可能性が高くなります。
また、弁護士に依頼すると相手との交渉をすべて任せられるため、ストレスや不安も大きく減らすことができます。弁護士が出ることでこちらの本気度が伝わり、相手が離婚に応じる可能性もあるでしょう。
話し合いがまとまらず「調停」や「裁判」に発展した場合も、弁護士のサポートは非常に重要です。
例えば、調停に同席してもらえたり、裁判で代わりに主張してくれたりと、全面的なサポートを受けることが可能です。
ただし、弁護士に相談・依頼する際は「弁護士費用」がかかるため、事前に確認が必要です。
協議離婚にかかる弁護士費用
弁護士費用は法律事務所によって異なりますが、一般的に「30万~80万円」が相場とされています。内訳は下表をご覧ください。
| 相談料 | 1時間あたり5000~1万円 |
|---|---|
| 着手金 | 20~30万円 |
| 成功報酬 | 20~30万円+経済的利益の10~20% |
| 諸経費、日当、実費など | 数万円 |
「着手金」は成果にかかわらず支払うのが基本ですが、「成功報酬」の定義は事務所によって異なります。そのため、何を成功とみなすのか、相談時によく確認しておくことをおすすめします。
協議離婚に関するQ&A
- Q:
-
協議離婚には証人が必要となりますか?
- A:
-
協議離婚自体に証人は不要ですが、離婚届には証人2名の署名が必要となります。
というのも、離婚は当事者や子供の将来に大きな影響を与えることから、不正などを防ぐ目的で、第三者の関与が必要と考えられているためです。なお、証人が何らかの法的責任を負ったり、不利益を被ったりすることは基本的にありません。
証人は、当事者を除く18歳以上の成人であれば誰でもなることができます。一般的に両親や兄弟、親しい友人などに頼むケースが多いでしょう。18歳以上であれば自分の子供を証人にすることもできます。
また、弁護士に依頼して証人になってもらうことも可能です。離婚届の書き方は、以下のページで詳しく解説しています。
合わせて読みたい関連記事
- Q:
-
離婚の協議に立会人は必要ですか?
- A:
-
離婚の協議の場に、立会人は不要です。
協議離婚は夫婦の話し合いで成立するものなので、第三者が同席する必要はないとされています。また、「離婚協議書」の作成時も、立会人や証人をつける必要はありません。もっとも、夫婦仲が非常に悪く話し合いにならない場合や、立会人がいた方が安心という場合は、呼ぶことも可能です。
なお、離婚協議書に立会人の署名や押印を加えても、効力に影響することはありません。
- Q:
-
協議離婚の成立後、取り消すことはできますか?
- A:
-
相手の詐欺や脅迫によって離婚が成立した場合、離婚の取消しが認められる可能性があります。
例えば、以下のようなケースです。- 相手が不倫相手と再婚するため、「多額の借金ができた」などと嘘をついて離婚を求めてきた
- 暴力や刃物で脅され、無理やり離婚届を書かされた
離婚の取消しを求める場合、騙されたと知ったとき又は脅迫が終了したときから3ヶ月以内に、家庭裁判所へ「協議離婚取消しの調停」を申し立てる必要があります。
調停で相手と合意できれば、裁判所が「合意に相当する審判」を下し、離婚が取り消されます。相手と合意できず調停不成立となった場合、「協議離婚取消しの裁判」を起こし、裁判所に判断を委ねることになります。
協議離婚で不安なことがあれば弁護士にご相談ください
協議離婚は手間や費用がかからないため、離婚について争いがない夫婦にはおすすめの方法です。
しかし、一方が離婚を拒否している場合や、離婚条件で揉めている場合、話し合いがスムーズに進むとは限りません。いつまでも離婚できず、ストレスが溜まる方もいるでしょう。
話し合いが行き詰ったときは、弁護士の力を借りるのがおすすめです。弁護士からアドバイスやサポートを受けることで、相手が早く離婚に応じてくれたり、より有利な条件で離婚できたりする可能性があります。
また、慰謝料や財産分与の金額なども適切に判断できるため、損をするリスクも抑えることができます。
協議離婚にご不安がある方は、ぜひお気軽に弁護士へご相談ください。
まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

- 監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
- 保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)
弁護士法人ALG&Associates 事務所情報
お近くの事務所にご来所いただいての法律相談は30分無料です。お気軽にお問い合せください。
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。
- 関連記事













