合意分割とは?手続きの流れや3号分割との違い

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
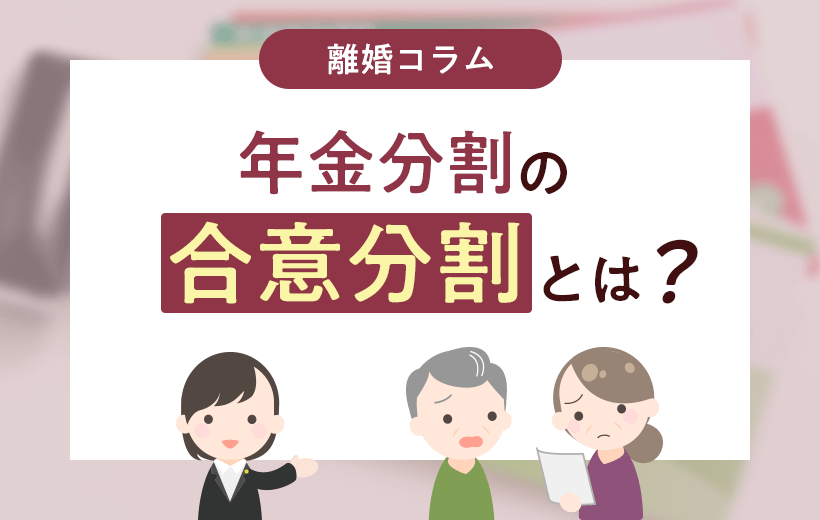
年金分割とは、夫婦の厚生年金記録を、離婚時に分割する制度です。
例えば、夫婦ともに民間の会社員で、妻が妊娠・出産を機に仕事を辞めて専業主婦になったケースなどで利用されています。この場合、妻は家事や育児に従事し、夫を支えてきたにもかかわらず、厚生年金に加入していないため、離婚後に受け取れる年金額は夫より低額になってしまいます。
夫が納めた厚生年金保険料の納付実績の一定割合を妻に分割することで、妻の年金額を増やし、夫婦間の不公平さを解消させることを目的としています。
また、年金分割には「合意分割」と「3号分割」という2種類の制度があります。本記事では、このうちの「合意分割」に焦点をあてて詳しく解説していきます。
年金分割のしくみは以下の記事でも解説していますので、こちらもぜひご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います
離婚問題ご相談予約受付来所相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。
※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
お電話でのご相談受付
0120-979-039
24時間予約受付・年中無休・通話無料
メールでのご相談受付
メールで相談するこの記事の目次
年金分割の合意分割とは?
合意分割とは、離婚時に、夫婦の婚姻生活中の厚生年金記録(年金額の計算の基礎となる標準報酬額)を、多い方から少ない方へ分割する制度です。「年金額そのもの」を分割するのではありません。
どの位の割合で分けるのか(=按分割合)は、夫婦の合意や裁判所の決定により定められますが、最大で2分の1となっています。また、年金分割を受ける側が元々受け取る予定だった年金受給額を下回らないようにする必要があります。
例えば、婚姻期間中の夫婦の厚生年金の標準報酬の総額が、夫が7000万円、妻が3000万円の合計1億円だったと仮定します。合意分割では、この1億円を分割するというイメージです。
この場合、元々の割合は、「夫7:妻3」ですが、合意分割により、最大で「夫5:妻5」へ、つまり、夫の標準報酬を5000万円(2000万円減額)に、妻の標準報酬を5000万円(2000万円増額)まで、改定できることになります。
この「7:3」から「5:5」までの割合のことを按分割合といい、合意分割制度では、夫婦の話し合いなどによってこの割合を定めなければなりません。
3号分割との違い
3号分割は、平成20年4月1日に施行された制度です。
国民年金の第3号被保険者(専業主婦や扶養内のパートタイマーなど)が、国民年金の第2号被保険者(民間のサラリーマンや公務員、教員など)である元配偶者の厚生年金保険料の納付実績の50%を分割するよう請求できる(=自分自身の納付実績とする)制度です。
「夫が会社員として働いて厚生年金保険料を払えたのは、外で仕事をせずに家事や育児で家を守り、夫を支えた妻のお陰であるから、夫の報酬30万円のうち15万円は当然に妻が稼いだものとする」というイメージです。
合意分割とは異なり、元配偶者の合意や裁判所の決定は必要なく、年金事務所に請求するだけで手続きが完結しますが、施行前である平成20年3月以前の婚姻期間は3号分割の対象とはなりません。
3号分割制度について詳細を知りたい方は、以下の記事もご参照ください。
合わせて読みたい関連記事
合意分割が適しているケース
3号分割は、元配偶者の合意や裁判所の決定を得る必要はなく、国民年金の第3号被保険者が年金事務所に請求するだけで手続きが完結します。手続きが簡単である一方、平成20年3月以前の婚姻期間は分割の対象とならない点に注意が必要です。
そのため、夫婦の婚姻期間や、働いていた期間などの諸条件によっては、合意分割の方が請求者の将来の年金額が増加するケースがあります。
例えば、
平成20年3月以前から、妻が国民年金の第3号被保険者(専業主婦や扶養内のパートタイマーなど)として、夫(国民年金の第2号被保険者)の扶養に入っていた場合
合意分割の「按分割合」の決め方
まずは話し合いで決める
合意分割では、まず夫婦間で、「厚生年金保険料の納付実績をどの位の割合で分けるのか」、つまり「按分割合」をどうするかを話し合います。
按分割合は、「元々の持分割合から50%の範囲」内で定めなければなりません。
例えば、婚姻期間中の夫婦の厚生年金の標準報酬額(年金額の計算の基礎となるもの)の総額の実績が、夫が7000万円、妻が3000万円の総額1億円だったとします。
現時点では、1億円のうち、「夫70%:妻30%」という割合ですが、合意分割では、「夫70%:妻30%」から「夫50%:妻50%」(=夫5000万円、妻5000万円の納付実績とする)までの範囲内で、按分割合を自由に定めることができます。そのため、例えば「夫60%:妻40%」などと定めても問題はありません。
一方、たとえ当事者の合意があっても、以下のような按分割合は認められません。
- 元々の割合(年金分割を請求する側が元々受け取る予定だった年金受給額)を下回るもの
〈例〉「夫80%:妻20%」 - 50%の範囲を超えるもの
〈例〉「夫40%:妻60%」
「情報通知書」を参考に決める
年金分割を行うときは、年金事務所などから「年金分割のための情報通知書」(通称「情報通知書」)を取り寄せなければなりません。
この情報通知書には、夫婦の氏名や基礎年金番号などの基本情報のほか、
- 婚姻期間
- 婚姻期間中の標準報酬の総額
- 按分割合の範囲
などが記載されています。
この情報通知書を確認しなければ、そもそも年金分割が可能なのかどうかや、按分割合の下限など、年金分割をするために必要な情報が判明しません。情報通知書は、合意分割であるか3号分割であるかを問わず、必要な書類となりますので、早めに取り寄せて内容を確認しましょう。
合わせて読みたい関連記事
まとまらなければ調停または審判
合意分割では、夫婦の合意によって按分割合を決めるのが基本です。そのため、話し合いが難航したり、相手が話し合いに応じてくれなかったりすると、いつまでも年金分割の取り決めを行うことができません。
このような場合、家庭裁判所に調停または審判を申し立て、裁判所(調停委員会)を挟んで話し合いを進めることができます。夫婦だけで話し合うよりも、スムーズに解決できる可能性が高まるでしょう。
合意分割の手続きの流れと必要書類
合意分割の手続きは、基本的に以下の流れで進みます。
- ①情報通知書の請求
↓ - ②按分割合の話し合い
- ③離婚等の成立(婚姻の取消し、事実婚の解消)
↓ - ④標準報酬の改定請求(年金分割の請求手続き)
↓ - ⑤改定・決定
④の改定請求は、離婚等の成立の翌日から2年以内に請求しなければなりません。
なお、②の按分割合の話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に調停または審判を申し立て、按分割合を決定してもらい、その後に標準報酬の改定請求を行います。この場合、離婚等の成立から2年が経過していても、裁判所の決定から6ヶ月以内であれば、改定請求が可能です(令和2年8月3日以降に離婚が成立した場合に限ります)。
また、④の改定請求をするときまでには離婚等が成立している必要がありますが、②の按分割合の話し合いの時点で離婚等が成立している必要はなく、離婚の協議や調停、裁判と同時並行で行うことができます。
合わせて読みたい関連記事
合意分割を考える際の注意点
対象となる年金には種類がある
日本では、基本的に、20歳から60歳の方は職業を問わず、全員「国民年金」への加入が義務付けられています。そして、民間の会社員や公務員、教員の方は、国民年金に加えて「厚生年金」に加入し、厚生年金保険料を納めています。年金分割制度で分割できるのは、婚姻期間中の「厚生年金」の記録だけであり、「国民年金」や「確定拠出年金」(iDeCoやNISAなど)は、分割の対象とはなりません。
詳しくは以下のページで解説していますので、併せてご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
対象となる年金に加入していた期間が対象
年金分割の対象期間は、婚姻期間のうち、対象となる年金に加入していた期間です。なお、合意分割は、制度が作られた平成19年4月1日以降に離婚したケースで利用できるものですが、それより前の婚姻期間も分割の対象に含まれます。
請求期限は離婚した翌日から2年
年金分割の請求期限は、離婚した日の翌日から数えて2年というのが基本的なルールです。ただし、按分割合を決めたものの、離婚後、年金事務所への請求手続きをする前にどちらかが亡くなった場合には、請求期限は亡くなった日から1ヶ月以内に短縮されます。
一方、以下のケースでは、例外的に請求期限を過ぎても年金分割の請求が認められます。
請求期限が来る前(離婚が成立した日の翌日から2年以内)に、年金分割に関する調停または審判を申し立てた場合
調停や審判は長引くこともあり、請求期限内に結果が出るとは限りません。そのため、調停の成立または審判の確定日が請求期限を過ぎても、年金分割を請求することが認められています。
ただし、延長期間は以下のように異なるため注意が必要です。
・調停の成立または審判の確定日が、令和2年8月3日以降の場合→その日の翌日から6ヶ月以内
・調停の成立または審判の確定日が、令和2年8月2日以前の場合→その日の翌日から1ヶ月以内
まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います
離婚問題ご相談予約受付来所相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。
※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
お電話でのご相談受付
0120-979-039
24時間予約受付・年中無休・通話無料
メールでのご相談受付
メールで相談する合意分割に関するQ&A
- Q:
相手が合意分割に応じてくれません。まだ離婚成立前ですが年金分割の請求は可能ですか?
- A:
年金事務所への年金分割の請求手続きは離婚後にしかできませんが、年金分割の取り決め自体は離婚成立前でも可能です。
なお、相手が合意分割に応じてくれず、離婚の話し合いも進んでいないようであれば、家庭裁判所に「離婚調停」を申し立て、調停手続きのなかで離婚と併せて年金分割についても話し合っていくという方法があります。調停不成立となった場合には「離婚裁判」と併せて年金分割についても申し立て、裁判所に最終的な判断を求めることになります。
- Q:
3号分割の手続きをした後に、合意分割も可能だったことがわかりました。追加で手続きは可能ですか ?
- A:
年金分割の請求期限前であれば、追加での手続きは可能です。
合意分割と3号分割どちらも適用される方は、早めに手続きをとるようにしましょう。また、3号分割の手続きを先に行い、後から合意分割の手続きをとっても問題ありません。
注意すべきなのは、「離婚時に第3号被保険者(専業主婦など)であれば、3号分割もできる」というわけではありません。3号分割の対象期間は、その制度が開始された後に限られるためです。
そのため、結婚した時期によっては、合意分割しか適用されないケースもあることに注意しましょう。ご自身が対象となるのはどの手続きなのか、きちんと判断することが重要です。
- Q:
合意分割は拒否できますか?
- A:
合意分割をするためには、離婚する(離婚した)夫婦の合意か、合意に代わる裁判所の決定が必要です。そのため、こちらが合意分割を拒否したとしても、相手は家庭裁判所に調停手続きや審判手続きを申し立てる可能性があります。
調停手続きの場合、成立には当事者双方の合意が必要なので、こちらが拒否すれば成立することはありません。しかし、審判手続きでは、裁判官が合意分割や按分割合について判断を行うため、基本的に合意分割を拒否することはできません。
下記の記事では、年金分割の拒否について詳しく解説していますので、こちらも併せてご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
- Q:
公正証書に財産分与はしないことを明記しています。離婚後、相手から合意分割したいと言われていますが、応じるべきでしょうか?
- A:
離婚成立日の翌日から2年が経っていなければ、合意分割の請求を拒否することは難しいでしょう。
財産分与と年金分割は異なる制度ですので、たとえ財産分与をしないことが公正証書で定められていても、請求期限内であれば相手は合意分割を請求できます。また、こちらが合意分割を拒否しても、相手は調停や審判を申し立て、裁判所に判断を委ねることができます。最終的には裁判所の決定に従う必要があるため、請求期限内に合意分割の請求がされたときは、調停や審判に発展することも想定したうえで、話し合いに応じるか検討する必要があります。
年金分割(合意分割)をしないのであれば、その旨離婚協議書(公正証書)等に明記しておきましょう。ただし、年金分割を行わない旨合意しても、3号分割については制限することができないのでご留意ください。
合意分割の交渉や手続きは弁護士にお任せください
年金の合意分割制度は、離婚したあとの老後の生活にとって非常に重要な制度ですが、一般の方にとっては聞きなれない用語も多く、年金額の計算や制度の内容も、複雑に思われる方が多いでしょう。加えて、合意分割には期限があります。
弁護士法人ALGには、離婚や合意分割制度などの家事事件に精通した経験豊富な弁護士が、多数在籍しています。
「制度の仕組み自体がよくわからない」
「そもそも、合意分割ができるのか?」
「まず何を準備すれば良いのか?」
「相手から合意分割を拒否されてしまった」
「年金分割の審判を申し立てられたが、どうすれば良いのか?」
など、年金の合意分割制度について少しでも不安やお困りのことがあれば、ぜひお早めに弊所の弁護士までご相談ください。
まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

- 監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
- 保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)













