離婚で父親が親権を獲得するためのポイント|不利な理由など弁護士が解説

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
「子供の親権者には、母性を有する者が望ましい(母性優先の原則)」という考え方があり、一般的に父親が親権を得られる可能性は低いといわれています。
親権とは、未成年の子供に不利益が生じないように養育や監護を行い、財産を管理して子供の代理で法律行為をする権利・義務のことです。日本では現在、離婚後は父母どちらか一方が親権を持つ単独親権が採用されていますが、2026年までに“共同親権”が施行予定となっています。
本記事では、父親が親権を獲得するにはどうすれば良いか悩んでおられる方に向けて「父親が親権を獲得するためのポイント」について詳しく解説していきます。
まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います
離婚問題ご相談予約受付来所相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。
※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
お電話でのご相談受付
0120-979-039
24時間予約受付・年中無休・通話無料
メールでのご相談受付
メールで相談するこの記事の目次
なぜ父親は親権獲得に不利なのか?
父親が母親よりも親権を獲得しにくい理由には、次のような事情があります。
- 母性優先の原則
- 監護継続性の原則
- 兄弟姉妹不分離の原則
- 子供の意思の尊重
- 監護体制の優劣
- 面会交流に関する寛容性の原則
一般的に父親は、フルタイムで働いている方が多く、子供と接する時間が制限されています。そのため、子供と多くの時間を過ごし接してきた母親が、子供の親権者に相応しいと判断されやすいです。こうした父親の養育実績の他、母性優先の原則や監護継続性の原則などにより、父親は親権を獲得しにくいといわれています。
では、「母性優先の原則」「監護継続性の原則」「兄弟姉妹不分離の原則」とは、一体どのような事情なのでしょうか?
それぞれの事情について、次項で詳しくみていきましょう。
母性優先の原則
母性優先の原則とは、「子供にとって母親は不可欠な存在であるため、父親よりも母性を有する母親と一緒に暮らした方が良い」という考え方です。特に子供が乳幼児(0~5歳)の場合は、母乳を与える時期でもあるため、きめ細かな監護ができる母親とは離すべきではないとされています。この原則は、子供の親権争いにおいて、母親が有利になる大きな要因のひとつです。
しかし近年では、共働きの世帯が増加し、子供の監護を主に父親が行っている家庭も増えつつあります。そのため、母性を有する者が優先されるのではなく、きめ細やかな監護ができる方が子供の親権者に相応しいと判断される傾向にあります。
監護継続性の原則
監護継続性の原則とは、「現状の子供の養育が安定しているのであれば、これまで育ってきた環境を変えずに現状を維持すべき」という考え方です。子供の現状が不安定なのであれば、子供のために環境を変える必要がありますが、そうでないなら現状維持が推奨されます。
夫婦が別居し、子供が一定期間一方の親と暮らして安定的な生活を送っていた場合は、「親権者を他方に指定する事情は特段ない」とし、子供と暮らす親に親権を認めるケースが多いです。
兄弟姉妹不分離の原則
兄弟姉妹不分離の原則とは、「一緒に暮らしている兄弟(姉妹)を分離するのは望ましくない」という考え方です。子供が両親だけでなく兄弟姉妹とも離れてしまえば、子供の心理的負担はさらに大きくなります。そのため、兄弟姉妹が離れ離れにならずに一緒に引き取れる親が有利になるという原則です。
兄弟姉妹を分離させて養育するのは、子供の利益ではなく、親の利益を優先しているに過ぎません。
子供の意思の尊重
子供本人の意思を尊重することは、子供の利益に直結します。
とはいえ、子供の年齢によっては、意思能力が乏しく、信憑性に欠けるでしょう。
具体的には、以下のような対応が取られます。
| 乳幼児~10歳前後 | 意思能力が乏しいと判断され、意思以外の判断基準が重視される |
|---|---|
| 10歳前後~14歳 | 意思能力が認められ、ある程度子供の意思が考慮される |
| 15歳以上 | 審判・訴訟時に子供への意見聴取が行われ、子供が親を選べる |
実務上では、10歳以上だとある程度子供の意思が反映されます。特に子供が15歳以上の場合は、かならず子供に意思確認を行わなければならないと法律で定められています。また近年では、子供の意思を尊重するべきだという考え方がさらに広がってきています。
監護体制の優劣
監護体制の優劣とは、「子供にとって、より良い生活環境を提供できる親を親権者とするべき」という考え方です。ここでいう生活環境には、経済状況や住まい、家庭の安定性、教育環境などが含まれます。
子供が安心して健やかに成長するためには、経済的な安定も大切ですが、それだけでは不十分です。たとえ収入が多くても、家庭内の雰囲気が悪かったり、子供に十分な愛情やケアが与えられていなければ、親権者として適切とはいえません。
そのため、経済力はあくまで判断材料の一つにすぎず、最も重視されるのは、子供が安心して暮らせる環境が整っているかどうかです。仮に父親の方が経済的に安定していても、母親が養育費や公的支援を活用して子供に必要な環境を整えられるのであれば、経済力の差だけで判断されることはありません。
面会交流に関する寛容性の原則
面会交流に関する寛容性の原則とは、「面会交流に協力・寛容的である方の親が親権者に相応しい」という考え方です。
面会交流は、子供が父母双方から愛されていると感じ、健やかに成長していくために必要な機会です。そのため、面会交流に協力的で他方の親に寛容的である親の方が、子供の利益(しあわせ)につながるとし、親権者を判断する際の考慮要素とされています。
ただし、相手が子供を虐待するなど、面会交流により子供が危険な目にあう可能性が考えられる場合には、この限りではありません。
父親が親権を取れる確率は?
父親が親権を獲得できる確率は、約11~13%前後と低く、厳しい現状です。
近年、共働き家庭は増加傾向にあるものの、やはり父親である男性が仕事をし、母親である女性が育児を行う家庭がまだまだ多いです。その結果、母親の方が子供と過ごす時間が多くなり、監護実績が豊富である母親が親権を獲得しやすい実情となっています。
まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います
離婚問題ご相談予約受付来所相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。
※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
お電話でのご相談受付
0120-979-039
24時間予約受付・年中無休・通話無料
メールでのご相談受付
メールで相談する父親が親権争いで有利になる3つのケース
状況によっては、親権争いで父親が有利になるケースもあります。
具体的に父親が親権争いで有利となるケースは次のような場合です。
- 母親が育児放棄をしている場合
- 母親が子供を虐待している場合
- 子供が父親と暮らすことを望んでいる場合
それぞれ詳しく解説していきましょう。
母親が育児放棄をしている
母親による次のような育児放棄とみられる行動がある場合は、親権者としてふさわしくないと判断され、親権が父親になる可能性は高いでしょう。
- 食事を与えない
- お風呂に入れない
- 掃除・洗濯などをせず、子供の生活環境が不衛生な状態にある
- 学校に行かせない
- 病気やケガをしても病院に連れて行かない
- 子供をほったらかしにして、ギャンブルしたり、夜遅くに外出したりする など
上記の母親の行動を証明するために、裏付ける資料が必要になるため、日々の妻が育児放棄している状況を記載した日記や写真・動画を残しておくようにしましょう。
合わせて読みたい関連記事
母親が子供を虐待している
母親が子供を虐待しているケースもまた、父親が親権を得るうえで有利にはたらくといえます。
身体的暴力、言葉の暴力、性的暴力など、その態様はさまざまです。虐待の事実を証明できる証拠がある場合には、より有利となるでしょう。
例えば、
- 虐待を受けたことがわかる写真や音声データ
- 子供本人や周囲からの証言
- 学校や行政機関への相談記録
などが、有用な証拠になる可能性があります。
子供が父親と暮らすことを望んでいる
子供自身の意向も、親権者を判断するうえで考慮されます。
ただし、子供の年齢によっては判断能力に欠ける時期もあるため、判断の重みが変わります。たとえば、乳幼児から10歳前後までは、子供に十分な判断能力がないと考えられているため、子供の意思以外の要素が重視されます。
一方で、子供が10歳前後になれば、意思能力が十分にあるとみなされ、ある程度子供の意思が尊重されます。特に15歳以上の場合は、審判・訴訟時に子供への意見聴取を行わなければなりません。
また、子供に言い聞かせたり、説得したりして、自分を選ぶように仕向けるなどの行為は控えましょう。「子供のしあわせ」を第一に考えて、子供の意見を尊重することが大切です。
父親が親権獲得のために押さえるべき5つのポイント
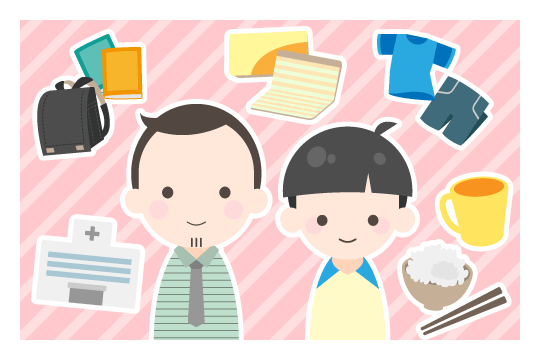
父親が親権を獲得するために最も重要なことは、子供の立場で「子供のしあわせ」を考えて実現できるか、追求できるかという点です。
子供にとってより有益とされる方が親権者となりますが、そう判断されるには、以下のようなポイントがあります。
①養育実績を積み上げる
子供の親権を得るためには、これまでどれだけ積極的に育児に携わってきたのか、養育実績があるかどうかが重要です。
しっかりと今までどのように育児をしてきたかが客観的にわかる資料を揃えましょう。
例えば、次のようなこれまでの育児に対する姿勢があれば考慮されるでしょう。
- 毎日、子供と一緒に入浴するようにしている
- 保育園や学校の連絡ノートを書いたり、送迎を行ったりしている
- 学校・習い事などのイベントに必ず参加している
- 洗濯・掃除・食事の支度のサポートをしている
- 子供の健康管理(病院への同行、予防接種の付き添い)を行っている など
これらを証明できるように、日頃から具体的にどのように子供の育児に携わってきたかを日記に記載しておいたり、写真や動画を撮影していたり、育児を積極的に携わってきたことを知っている親族や知人に証言してもらったりしておきましょう。
②子供と過ごす時間を確保する
父親が親権を獲得するには、子供と過ごす時間を確保できるかどうかが重要となります。
たとえば、残業や休日出勤を控え、不在時には祖父母に子供の面倒をお願いするなどし、子供優先のライフスタイルを確立できると、親権を獲得しやすいでしょう。
両親が揃っていない家庭であることに、子供は不安や寂しさを覚えます。それに加え、住み慣れた土地からの引っ越しや転校等による生活環境の変化は、さらに子供の心身の負担を増加させます。そのため、極力子供と過ごす時間を確保し、子供の心身の負担を軽減させることが大切です。
③離婚後の経済状況
親権を獲得するには、離婚後の経済状況も重要な要素に含まれます。
父親が親権を望む場合、“父親の経済状況(資産や収入など)”が重視されます。共働き夫婦の増加に伴い、女性である母親にも経済力がある家庭が増えていますが、離婚前の生活環境と変わらずに生活できることがベストです。
一般的には、母親に比べて父親の方が、経済力があり安定している場合が多いため、離婚前の生活環境を変えずに生活できる点を主張していきます。
経済力が高ければ高いほど親権を得られる確率が高くなるわけではありませんが、子供が健やかに成長できると考えられる経済力があるかどうかは重視されます。
④虐待・育児放棄・DVなどの証拠を集める
母親が子供を虐待・育児放棄・DVしている場合は、それらを証明する証拠を集めましょう。
たとえば、次のような証拠があると、親権を獲得できる可能性を高められます。
- 虐待を受けたことがわかる写真や音声データ
- 母親の行動を記した日記
- 育児放棄や家事をしていないことがわかる家の状況の写真
- 食事が作られていないことがわかる写真(冷蔵庫の中など)
- 母親が育児放棄をしていることを示すメールのやりとり など
これらの証拠があれば、父親の親権獲得に有利に働きます。母親が子供の育児を十分に行っていないと証明できれば、「子供の育児は父親が殆ど行っていた」と評価されやすいです。
⑤離婚問題に強い弁護士に相談する
離婚問題に強い弁護士への相談は、父親の親権獲得に大きく近づけます。
弁護士であれば、父親が親権を獲得するためのサポートが行えるからです。
特に離婚問題に精通した弁護士に相談・依頼することで、次のようなメリットを得られます。
<弁護士に相談することで得られるメリット>
- 父親の養育実績を積み上げるためのアドバイスをもらえる
- 親権についての交渉を弁護士に一任できる
- 母親が育児放棄や虐待をしている場合、有効となる証拠を集めてもらえる
- 母親や裁判官、調停調査官などへの主張や立証を適切に行ってもらえる
- 父親が親権を獲得するための的確なアドバイスを受けられる など
これらのメリットを受けることで、父親が親権を獲得できる可能性が高まります。
父親が親権を獲得する流れ
- ①夫婦間で話し合う
まずは離婚する際に、夫婦で話し合って親権者を決めます。子供が複数いる場合は1人ずつ親権者を定めます。
夫婦の話し合いで、離婚と親権者について合意ができれば、離婚届に親権者を記載して役所に提出して受理されれば協議離婚が成立して親権者が決まることになります。
ただし、親権で揉めた場合は、離婚自体ができません。 - ②離婚調停を申し立てる
夫婦間での話し合いで親権者が決まらなければ、家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。
離婚調停では、裁判官や調停委員を交えて、親権をはじめ、財産分与、養育費など離婚に関する条件を話し合います。調停の話し合いで親権者が決まらないときは、家庭裁判所調査官によって、子供に意見を聞いたり、家庭訪問や学校訪問をしたりして調査を行う場合もあります。 - ③離婚裁判を提起する
離婚調停の話し合いでも親権者が決まらなければ、調停不成立となります。
調停不成立後は、離婚裁判を提起して、裁判官が親権者について判決を下します。
なお、離婚調停で概ね離婚について合意できてはいるが、親権者のみ争っており、夫婦が裁判所の決定に委ねる合意をしているのであれば、調停不成立後、審判手続きに移行して、裁判官が親権者について判断を下す場合もありますが、割合的には非常に少ないです。
離婚調停で親権者を判断するポイントと母親が不利になるケースについては下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
父親が親権を獲得した場合、養育費を請求できる?

父親が親権を獲得した場合は、母親に養育費を請求できます。
親は子供を扶養する義務を負います。
離婚して、夫婦でなくなっても、親子である関係は変わりません。
したがって、離婚をして母親が親権者でなくなっても、親として子供を扶養する義務は負いますので、養育費を支払わなければいけません。
ただし、養育費の金額は夫婦それぞれの収入を考慮します。
親権者となった父親の収入が高く、支払う側の母親に支払能力がない場合は養育費の負担が少なくなるケースや免除されるケースもあり得ます。
合わせて読みたい関連記事
父親が親権を得られなくても面会交流で子供に会える?

親権を得られなかった場合でも、面会交流を通して子供に会える可能性は十分にあります。
面会交流は、親の事情は抜きに、「子供のしあわせ」を重視して行われるものです。子供の健やかな成長のためには、離れて暮らす親との交流は何よりもの糧となるでしょう。
この実現は、たとえ離婚したからといっても、親として果たさなければならない義務ですので、親権者の一方的な都合で拒否できるものではありません。
親権獲得が難しいようであれば、親権を譲る代わりに面会交流を認めるよう交渉することなどを検討してみましょう。
面会交流についての詳細は、下記のページをご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
離婚前に母親が子供を連れ別居した場合はどうしたらいいのか?
相手(母親)が子供を連れて別居した場合は、決して実力行使で連れ戻してはいけません。
場合によっては、刑事責任に問われるおそれもあります。
まずは、相手と話し合いで子供を引渡してもらえないか交渉してみましょう。
話し合いでは応じてもらえないようであれば、「子の引渡し審判(または調停)」と「子の監護者指定審判(または調停)」を同時に申し立てしましょう。
審判(調停)の決着までには、数ヶ月の期間がかかりますので、一刻も早く子供を引渡してもらうために「審判前の保全処分」も一緒に申し立てて、仮に子供を引渡すよう求めることもできます。
相手が子供を連れて別居した時間が長くなればなるほど、現在の監護状況に問題なければ「現状維持の原則」という考えによって親権について相手に有利になる可能性があります。
一刻も早く弁護士に相談をして対応するようにしましょう。
連れ去られた子供を連れ戻す方法は下記ページで詳しく解説していますのでぜひご参考ください。
合わせて読みたい関連記事
弁護士の介入により父親の親権を勝ち取ることができた解決事例
幼い子供の親権を父親が勝ち取れた事例
幼い子供の親権を父親が獲得できた弁護士法人ALGの解決事例を紹介します。
依頼者は、精神的に不安定な相手と別居し、幼い子供とともに実母と同居している状態で、離婚と親権獲得を求めて、当事務所にご依頼くださいました。
ご依頼を受けた後、相手から「監護者の指定調停」を申し立てられましたが、このタイミングでは以下の懸念がありました。
- 別居時の態様が「子の連れ去り」と判断されるおそれがあったこと
- 依頼者はフルタイムの会社勤めをしていた関係で、別居前の育児実績があまりなかったこと
そのため、当面待ちの姿勢をとりつつ、その間に一日でも多く育児の実績を重ねるようアドバイスをしました。
その結果、長期間の育児実績が認められ、裁判所の調査官調査においても、「子供との関係性に問題はない」との判断を受けられました。最終的には、子供の親権を獲得して離婚が成立し、納得のいく結果で終わることができました。
離婚調停で親権について争った結果、父親が勝ち取った事例
離婚調停で親権について争った結果、父親が勝ち取った解決事例をご紹介します。
小学生の子供2人の父親であるご依頼者様は、妻(相手)が不倫をしていたことが発覚して言い争いになり、相手が実家に一人で戻るかたちで別居を開始しました。
相手の不貞行為が原因ということもあり、ご依頼者様は子供2人の親権と慰謝料を強く希望されて弁護士法人ALGにご依頼くださいました。
別居して1ヶ月後に離婚調停が申し立てられました。
相手が子供たちの親権を争ってきた場合は、今までの監護状況や子供の年齢などを考慮すると、相手が子供たちの親権者に指定される可能性が十分にありました。そこで、弁護士の方針として、監護実績を積むことを最優先にし、別居期間を引き延ばす方針を立てました。
別居期間中にご依頼者様の監護実績を積み、監護の内容を逐一、裁判所に証拠として提出していた結果、相手は親権をあきらめ、ご依頼者様が親権を獲得することができました。
慰謝料については、慰謝料に相当する養育費を増額することで合意ができました。
父親の親権に関するQ&A
- Q:
親権は父親で構わないが、育てるのは母親と主張されています。可能なのでしょうか?
- A:
「親権を持つ親」と「実際に子供を育てる親(=監護者)」を別々とすることは、不可能ではありません。しかし、裁判所は、この判断に消極的であるといえます。子供のしあわせを考えると、親権者と監護者は同一である方が好ましいとされているからです。
ご質問のケースでは、相手方とよく話し合って交渉していくことが望ましいですが、折り合いがつかないようであれば最終的に裁判所に判断してもらうことになるでしょう。そうなる前に一度弁護士に相談した方がいい事案でもありますので、迷われたら弁護士に問い合わせてみるのも一つの手です。
監護者を指定する手続きについて、詳しくは下記のページをご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
- Q:
父親が乳児の親権を得るのは無理なのでしょうか?
- A:
父親が乳児の親権を得るのは不可能ではありませんが、非常に難しいのが実情です。
その背景には、子供が幼ければ幼いほど、特に乳児の場合は、どうしても母親の存在が必要になることが多い点が関係しています。今までの先例においても、そして現状でも、圧倒的に母親が親権者となるケースが多いです。
ただし、母親が虐待や育児放棄をしているなどの事情があれば、父親が親権者となれる可能性は十分にあります。この場合、父親が育児をするのはもちろんですが、親族に協力してもらうなど、周囲のサポート体制を確保し整えておくと親権獲得に有利にはたらきます。
また、「母親が育児をするのは子供にとって悪影響である」ことを証明するために、母親による虐待や育児放棄の実態の証拠を集めておきましょう。
- Q:
未婚で生まれた子供の親権を父親が得ることは可能ですか?
- A:
未婚の男女の間に子供が生まれた場合、原則、子供を出産した母親の単独親権となります。結婚しない限り、父母の共同親権とすることはできません。
父親が親権を取るためには、まずは子供を認知して法律上の父子関係を明らかにする必要があります。そのうえで相手と協議し、合意に至れば父親が親権を取ることは可能です。
お互いに親権を譲らない場合には、裁判所の手続きを利用して親権者を決めていくことになりますが、実情としては、何らかの理由があって母親が子供を育てていくことが難しい場合などを除き、父親が親権を取るのは困難でしょう。
- Q:
離婚後、母親が育児放棄(ネグレクト)をしている場合は父親が親権を取り返すことはできますか?
- A:
離婚時に”母親”と定めた親権者を”父親”に変更することは可能です。
ただし、親権者の変更は、父母間の話し合いや簡易な手続きでは変更できません。
家庭裁判所に親権者変更調停を申し立てる必要があります。調停では、相手が育児放棄をしていることがわかる客観的な証拠を示しながら、「子供の福祉」に悪影響を及ぼしている事実を主張する必要があります。
場合によっては、家庭裁判所調査官が、子供に意見を聞いたり、家庭訪問・学校訪問をしたりして調査を行います。その結果、育児放棄をしている事実やこのままだと子供が健全な成長を妨げられていると裁判所に認めてもらい、親権者を変更するのが妥当だと判断されれば、親権者の変更が認められます。
親権の変更について、詳しくは下記のページをご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
父親が親権を獲得するためにも、離婚問題に強い弁護士にご相談ください
離婚することになり、親権を獲得したいけれど、父親は不利だとあきらめている方は、ぜひ弁護士にご相談ください。
確かに親権は母親がもつことが多いのが現状です。
しかし、弁護士にサポートしてもらいながら、養育実績を積み上げたり、離婚後の養育環境を整えたり、相手が育児放棄や虐待をしている証拠を集めたりできれば、父親でも親権を獲得できる可能性は十分にあります。
弁護士法人ALGでは、離婚案件を多く取り扱っており、父親が親権を獲得した成功事例も多数ございます。今まで培ったノウハウや経験を活かして、父親の親権獲得に向けて尽力いたします。
一度決めた親権者の変更はなかなか裁判所で認められませんので、離婚時の親権の決定は慎重に行うべきです。まずはお気軽に弁護士法人ALGにお問合せください。
まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

- 監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
- 保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)













