養育費を決める際に知っておきたい基本の知識

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
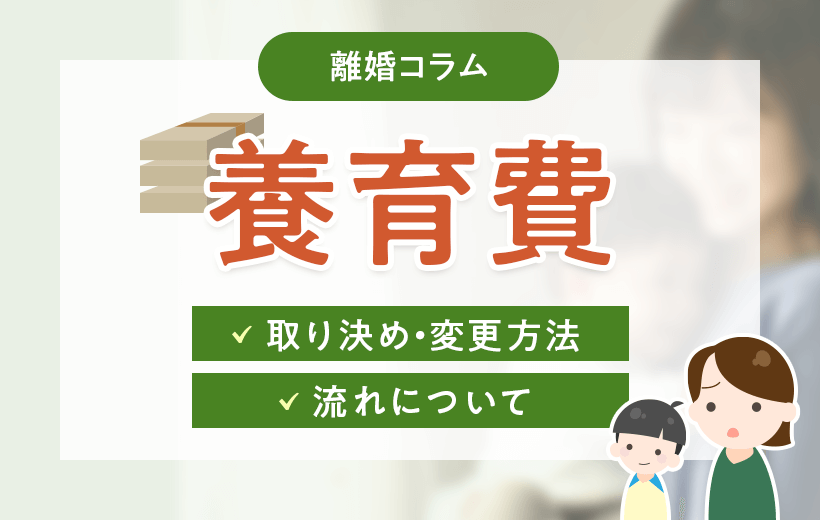
子供のいる夫婦の場合、親権をもたずに離婚しても子供の実親であることに変わりはないため、子供と離れて暮らす親は“養育費”を支払う必要があります。しかし、「養育費をいつまで支払う必要があるのか」「どのような手順で養育費を決めていくのか」など、養育費の支払いにさまざまな疑問を抱かれている方もいらっしゃるでしょう。
そこで本記事では、「養育費」に着目し、養育費の決め方や相場などについて、詳しく解説していきます。ぜひご参考になさってください。
まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います
離婚問題ご相談予約受付来所相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。
※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
お電話でのご相談受付
0120-519-116
24時間予約受付・年中無休・通話無料
メールでのご相談受付
メールで相談するこの記事の目次
養育費とは

養育費とは、子供を監護・教育するために必要な費用のことをいいます。
経済的・社会的に自立していない子供が自立するまでにかかる食費、住居費、教育費、医療費など生活するために必要なものです。
子供に対する養育費の支払義務(扶養義務)は、親の生活に余力があるかどうかに関わらず、自分と同じ生活を保障する「生活保持義務」という強い義務と考えられています。
よって、離婚する場合、子供と離れて暮らす親(非監護親)は子供と一緒に暮らし養育をする親(監護親)に養育費を支払う義務がありますから、離婚の際には養育費についてきちんと取り決めておくことが重要です。
合わせて読みたい関連記事
養育費はいつまで受け取れる?
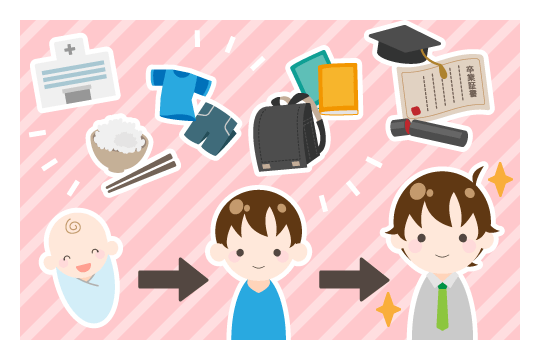
養育費の支払いは、基本的に満20歳までとされています。
これは、「20歳までは親から独立して生活できる段階ではない」と考えられているからです。
ただし、病気や障害などで就業や親からの独立が困難な場合には、20歳以降も養育費の支払いが必要となる場合があります。また、民法改正により成人年齢が18歳に引き下げられたため、「高校を卒業して就職した18歳には養育費が不要」と考えられる場合もあります。
とはいえ、養育費は両親が合意すれば、子供の年齢を問わずに養育費の支払期間を決めても問題ないとされています。そのため、両親が養育費について協議できるのであれば、養育費は柔軟に取り決められます。
養育費の支払期間について、さらに詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
養育費の決め方
「養育費を決めたい」あるいは「養育費を変更したい」場合は、以下の流れで手続きを進めます。
- ① 話し合いで決める
- ② 合意できたら公正証書に残しておく
- ③ 家庭裁判所の手続きで決める(調停・審判・裁判)
養育費の条件は、まず夫婦で話し合って決めることから始めます。
このとき、相手と直接交渉したくない、顔を合わせたくないと思われる方は、この段階から弁護士に相談されることをおすすめします。
弁護士であれば、相手との交渉をすべて一任してくれます。また、話し合いがまとまらなかった場合に裁判の手続きなども行ってくれるため、様々な負担が軽減されます。
①話し合いで決める
養育費に関する条件は、まず夫婦の話し合いで取り決めます。
話し合いでは、以下の内容を具体的に取り決め、養育費の支払いがスムーズに行われるようにします。
- 金額
- 支払期間(始期と終期)
- 支払日
- 支払方法
- 振込先 など
取り決めた内容は、トラブルに発展するのを防ぐため、書面(合意書)に残しておくと安心です。
また、相手が話し合いに応じない場合は、弁護士に依頼するか裁判所の手続きを進めた方が良いでしょう。相手と別居している場合は、内容証明郵便を送付します。
内容証明郵便は、いつ・誰が・誰に対して・どのような内容の書面を差し出したか郵便局が証明してくれるため、相手に心理的プレッシャーを与えられます。
内容証明郵便の出し方について、詳しくは郵便局の以下のページをご覧ください。
合意できたら公正証書に残しておく
当事者間の話し合いで合意した場合、その内容は「合意書」にまとめ、さらに「公正証書」のかたちで残しておきましょう。
公正証書は、高度な法的知識を持つ公証役場の公証人によって作成される文書です。そのため、裁判所では、個人間で作成した文書よりも信頼性の高い証拠として扱われるというメリットがあります。また、記載内容に“強制執行認諾文言”を入れてもらえば、約束した養育費が支払われないときに、強制執行の手段を取ることができるようになります。
公正証書のメリットや書き方などについて、下記ページでさらに詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
③家庭裁判所の手続きで決める(調停・審判・裁判)
話し合いでの解決が難しい場合は、調停や裁判等の手続きを利用します。
夫婦が話し合いで解決を図る協議離婚の次の手段として挙げられるのは、「離婚調停」です。
離婚調停では、夫婦の話し合いに裁判官や調停委員が入り、養育費に関する取り決めを行います。
離婚調停で話し合いがまとまると、離婚が成立して「調停調書」が作成されます。調停調書は、裁判の確定判決と同じ効力をもち、調停時に決めた養育費が支払われない場合は、強制執行の手続きで相手の給与や預貯金などの財産を差し押さえられます。
なお、調停委員会を交えた話し合いでも意見がまとまらず、調停不成立となった場合には、自動的に「審判」の手続きが開始され、裁判官によって判断がなされます。
離婚調停が不成立の場合は、最終手段として「離婚裁判」を提起し、裁判所に判断を求めます。
養育費の取り決めに関しては「養育費請求調停」を、変更に関しては「養育費増額請求調停」または「養育費減額請求調停」を申し立てます。
養育費の調停について、詳しくは以下のページをご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
養育費の相場はいくら?
養育費の相場は、「令和3年度全国ひとり親世帯等調査結果」によると、養育費の平均月額は母子世帯が5万0485円で父子世帯は2万6992円と公表されています。
また、子供の数別の養育費の平均相場は、下表のとおりとされています。
| 子供の数 | 母子世帯 | 父子世帯 |
|---|---|---|
| 1人 | 4万0468円 | 2万2857円 |
| 2人 | 5万7954円 | 2万8777円 |
| 3人 | 8万7300円 | 3万7161円 |
| 4人 | 7万0503円 | – |
しかし、実際は、養育費の金額を取り決める際に、平均相場ではなく裁判所が公表する「養育費算定表」を参考とするケースが多いです。また、父母双方の合意があれば、養育費はいくらでも構いません。
養育費の相場を知りたい方は、以下の計算ツールをご活用ください。
また、養育費を決める際に考慮される要素などについては、以下のページで詳しく解説しています。
ぜひ併せてご参考になさってください。
合わせて読みたい関連記事
養育費の相場は養育費算定表を目安にする
養育費の金額を決めるときに、養育費の目安になるとしてよく活用されているのが「養育費算定表」です。
裁判所のウェブページにも掲載されており、調停・審判・裁判の手続きで養育費を決めるときにも参考にされています。
養育費算定表は、非監護親と監護親それぞれの収入と収入形態(給与所得者か自営業者か)に子供の年齢と人数を考慮して、養育費の相場となる金額が算定できるようになっています。
養育費の増額請求はできる?
お互いの合意があれば、一度決めた養育費の内容を変更し、増額することができます。また、合意に至らなかったとしても、裁判所に認めてもらうことができたら、増額が叶います。
裁判所に増額が認められるために重要な条件は、“取り決めた当時では予想できなかった事情の変更”があったといえるかどうかです。例えば、次のような変化があった場合には、事情の変更があったとして、増額が認められる可能性があります。
- 病気を患うなどして、受け取る側の収入が減少した
- 昇給や転職などにより、支払う側の収入が増加した
- 子供が交通事故に遭い、多額の治療費が必要になった
養育費の増額請求について、詳しくは下記のページをご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
養育費は払わなくていい場合もある?
養育費を請求された人に特別な事情がある場合は、支払いが免除されることがあります。
養育費を支払わなくてもよい特別な事情は、以下のような場合です。
- リストラや病気により失業するも、就職先がなかなか見つからない場合
- 生活保護を受けている場合
- 養育費を受け取る側の収入が多い場合
- 養育費の支払いは不要だと、受け取る側に了承してもらえた場合
- 子供が元配偶者の再婚相手と養子縁組をした場合
- 子供が元配偶者の連れ子で、離婚を機に養子縁組を解消した場合
- 子供が20歳を迎えた場合
- 子供が就職して自立した場合 など
養育費の減額が認められるケース
養育費の増額と同様にお互いの合意、あるいは裁判所に認められれば、養育費の減額が可能です。
裁判所に認めてもらうには、予想できなかった“事情の変更”が必要です。
たとえば、次のような事情がある場合には、養育費の減額が認められる可能性があります。
- リストラに遭うなどして支払う側の収入が減少した
- 支払う側が再婚して扶養家族が増えた
- 受ける側が再婚して再婚相手と子供が養子縁組をした など
支払う側に生じた事情がもっともな場合には、調停や審判で養育費の減額が認められます。そのため、妥協点を探って交渉(話し合い)で解決を図るところから始めるとよいでしょう。
養育費の減額請求について、さらに詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
離婚後に相手が養育費を払わない場合の対処法
公正証書という確かな証拠があるにもかかわらず、相手が養育費を支払ってくれない場合には、裁判所へ「強制執行」の申立てを行いましょう。相手の給料や預貯金口座などを差し押さえる等して、未払い養育費の回収を図れるようになります。ただし、公正証書に“強制執行認諾文言”が付されていなければなりません。
養育費の強制執行については、下記のページで詳しく解説していますので、参考にしてみてください。
まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います
離婚問題ご相談予約受付来所相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。
※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
お電話でのご相談受付
0120-519-116
24時間予約受付・年中無休・通話無料
メールでのご相談受付
メールで相談する養育費に関するQ&A
- Q:
-
離婚の際、養育費を払わないと言われたらどうすればいいですか?
- A:
-
離婚する際に相手が養育費の支払いに応じない場合は、「弁護士に相談する」または「調停や裁判を利用する」必要があるでしょう。
弁護士は、養育費の支払いに応じるように相手と直接交渉してくれます。法律の専門家である弁護士からの主張により、相手が養育費の支払いに応じる可能性が高まります。
それでも応じない場合には、調停で裁判官や調停委員を介して話し合います。なお、それでも応じない場合は、最終手段として裁判を提起し、裁判官に判断を委ねるのが有効です。裁判所が決めた養育費は必ず支払わなければならず、支払いがなされない・支払いが滞る場合には、強制執行にて財産の差押えが可能です。
- Q:
-
離婚時に住宅ローンと養育費は相殺できますか?
- A:
-
住宅ローンと養育費の「法的な相殺」は認められていません。しかし、夫婦間で合意があれば、実質的に相殺することは可能です。
〇 相殺が可能なケース
住宅ローンの名義人である夫が家を出て、妻と子供が家に住むケース
夫:住宅ローンを返済する債務と養育費を支払う債務
妻:住宅ローンを夫に支払う債務
➡ 相殺できる× 相殺ができないケース
住宅ローンの名義人である夫だけが家に住むケース
住宅ローンの名義人である夫と子供が家に住むケース
夫:住宅ローンを返済する債務と養育費を支払う債務
妻:債務なし
➡ 相殺できないなお、法的な「相殺」とは、双方が金銭的な債務を負っている場合に、その債務を同額で打ち消し合うことを指します。したがって、どちらか一方に債務がない場合は、法律上の相殺は成立しません。
- Q:
-
再婚したら養育費の支払いはどうなりますか?
- A:
-
基本的には、再婚後も法律上の扶養義務を負うため、引き続き養育費を支払う必要があります。
しかし、離婚後に「事情の変更(再婚や収入の変動等)」がどちらかに生じた場合には、養育費の減額や免除を主張できる可能性があります。再婚では、以下のような事情が挙げられます。
<養育費の減額や免除の主張が可能な事情>
- 再婚相手と子供が養子縁組をした
- 再婚相手との間に子供が生まれた
- 再婚相手の連れ子と養子縁組をした
- 再婚相手の収入が低い など
なお、再婚を機に養育費の減額や免除を求めるには、まず元配偶者と話し合う必要があります。話し合いでまとまらなければ、養育費減額調停を申し立てます。
再婚後の養育費について、詳しくは以下のページをご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
- Q:
-
妊娠中に離婚しましたが、養育費は請求できますか?
- A:
-
妊娠中に離婚したとしても、離婚後300日以内に出産した場合は、前の夫の子供であるとみなされるため、養育費の請求は可能です。
一方、離婚後300日を経過した後に出産した場合、養育費を請求するためには相手(父親)に子供を認知してもらう必要があります。認知についての詳しい内容は、下記のページをご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
養育費について困ったことがあったら、弁護士にご相談ください
養育費を決めようにも、金額はいくらが適正なのか、どのように取り決めたらいいのか、合意書はどんな風に作成したらいいのかなど、判断に悩むこともあるでしょう。
養育費について困ったことがあったら、まずは弁護士にご相談ください。ご家庭によって置かれている状況は異なるため、養育費の問題を解決する方法も様々です。弁護士なら、法的知識に基づき、それぞれの事情に合わせた最善の解決策を考え、ご提案することができます。
また、相手との交渉を代わりに行う、裁判所への提出書類を作成するなど、養育費に関する手続きをサポートすることも可能です。養育費は、子供の今後に関わる大事な内容です。お悩みのときは、ひとりで抱え込まず、弁護士の力を借りることをぜひ検討してみてください。
まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

- 監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
- 保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)
弁護士法人ALG&Associates 事務所情報
お近くの事務所にご来所いただいての法律相談は30分無料です。お気軽にお問い合せください。
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。
- 関連記事
- 離婚時の養育費なしとする合意は有効か?養育費と扶養料の違いについて養子縁組した場合の子供の養育費|離婚で養子縁組を解消したらどうなる?生活保護と養育費の関係養育費の相場は?子供の人数や年収、考慮される要素などを解説養育費を払わない元配偶者へどうしたらいい?請求方法や時効について養育費の請求に関するよくあるご質問未払い養育費の回収方法|調停や強制執行の手続き、回収代行について養育費が支払われずお困りの方へ養育費の不払い|強制執行などの対処法・請求の時効養育費未払い対応は弁護士にお任せ下さい年収500万円の養育費相場はいくら?【子供の人数・年齢別 早見表付き】年収1000万円の養育費の相場はいくら?早見表や金額の決め方など年収300万円の養育費の相場|子供の人数・年齢別ケース【2019年】養育費算定表が改定されました。養育費に連帯保証人はつけるべき?メリットや方法について養育費の支払いは扶養控除の対象になる?要件や確定申告など扶養義務の範囲や養育費との違いをケース別で解説いたします妊娠中に離婚した場合の養育費年収別の養育費相場や基準となる年収の考え方について解説!養育費の支払いがある場合の自己破産|事前に確認すべき3つのこと養育費算定表とは?表の見方や相場について解説養育費の調停とは?流れや聞かれることなど押さえておくべきポイント養育費の受け取りや支払いに税金はかかる?(贈与税や扶養控除について)養育費の増額が認められる条件・請求する方法知っておきたい子供の認知と養育費の関係養育費の減額は拒否できるのか養育費の減額請求は可能?認められるケースや方法を解説養育費の時効は基本5年!止める方法、過ぎた場合についても解説再婚したら養育費の支払い義務はどうなる?減額・免除されるケースとは再婚を理由に養育費の免除や減額は認められるのか?なぜ養育費は公正証書で残すべきなのか?メリットや作り方など養育費の増額を拒否するには【養育費】法律上の支払い義務について|払わないとどうなるのか離婚後の養育費の支払いはいつまで?支払期間は変更できる?養育費の強制執行とは?手続きの流れや必要書類、注意点など養育費で強制執行された場合のデメリットは?回避する方法も解説養育費の一括請求|デメリットや注意点など知っておくべき知識













