どんな理由でも離婚はできるの? 民法770条で定められた法定離婚事由とは?

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
離婚すると決意した夫婦は、家庭ごとに様々な理由があります。
夫婦での話し合いや調停手続きで離婚する場合は、夫婦で離婚について合意ができれば、どんな離婚理由でも問題ありません。
しかし、離婚の合意ができなければ、最終的に「離婚裁判」を行うことになります。
離婚裁判では、夫婦の合意は必要なく、裁判上で離婚が認められる理由が必要となります。
裁判上で離婚が認められる理由とはいったい、どのようなものなのでしょうか?
本記事では、離婚理由ランキングをお伝えしたうえで、どんな理由でも離婚できるのか?民法770条で定める離婚を認める理由(法定離婚事由)とはどういうものなのか?などを詳しく解説します。
まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います
離婚問題ご相談予約受付来所相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。
※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
お電話でのご相談受付
0120-979-164
24時間予約受付・年中無休・通話無料
メールでのご相談受付
メールで相談するこの記事の目次
どんな理由で離婚するの? 離婚理由ランキング (男女別)
最高裁判所が公表していている令和3年度司法統計のデータでは、離婚原因のランキングは次のようになりました。
| 男性 | 女性 | |
|---|---|---|
| 1位 | 性格が合わない | 性格が合わない |
| 2位 | 精神的に虐待する | 生活費を渡さない |
| 3位 | 異性関係 | 精神的に虐待する |
| 4位 | 家族親族と折り合いが悪い | 暴力を振るう |
| 5位 | 浪費する | 異性関係 |
夫、妻ともに離婚理由のダントツ第1位は「性格が合わない(性格の不一致)」です。
ここ十数年、日本の離婚理由の不動の第1位となっています。
ここ数年で離婚理由として上昇しているのが、夫、妻ともに「精神的に虐待する」です。
いわゆるモラハラです。
夫婦間で身体的な暴力・虐待が少なくなっている一方で精神的な暴力・虐待が増えているということがわかります。
では、これらの離婚理由で、離婚が認められるのでしょうか。
後ほど、詳しくみていきましょう。
離婚方法によっては法的に認められる理由が必要
離婚する方法には、次のとおり主に3つの方法があります。
流れとしては協議離婚→離婚調停→離婚裁判と進めていきます。
| 協議離婚 | 夫婦間で話し合いをして離婚する方法 | 離婚する理由は問わない |
|---|---|---|
| 離婚調停 | 家庭裁判所で裁判官や調停委員を交えて話し合いをして離婚する方法 | 離婚する理由は問わない |
| 離婚裁判 | 家庭裁判所の判決で離婚する方法 | 法定離婚事由が必要 |
表のとおり、協議離婚と離婚調停は、夫婦で離婚の合意ができれば、離婚する理由は特段問いません。
離婚裁判は、民法770条1項各号に裁判上で離婚が認められる理由が定められており、夫婦それぞれの主張や提出した証拠などを総合的に鑑みて、裁判官が離婚について判断を下します。
離婚が認められる理由(法定離婚事由)のどれかに当てはまっていなければ、離婚は認められません。
法定離婚事由については、次項で詳しく解説します。
「協議離婚」「離婚調停」「離婚裁判」について、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
【民法第770条】法定離婚事由とは?
民法によって、一定の事由がある場合は、裁判を行うことによって離婚できるとされています。
この一定の事由を「法定離婚事由」といい、民法770条1項で、次の5つを離婚事由として定められています。
離婚したい理由が、5つのうちのいずれかに当てはまっている場合、離婚裁判を提起し、裁判所が離婚請求を認めると、相手が離婚を拒否していても離婚できるということになります。
民法第770条【裁判上の離婚】
①夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
- 一 配偶者に不貞な行為があったとき
- 二 配偶者から悪意で遺棄されたとき
- 三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき
- 四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
- 五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
②裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
配偶者に不貞な行為があったとき
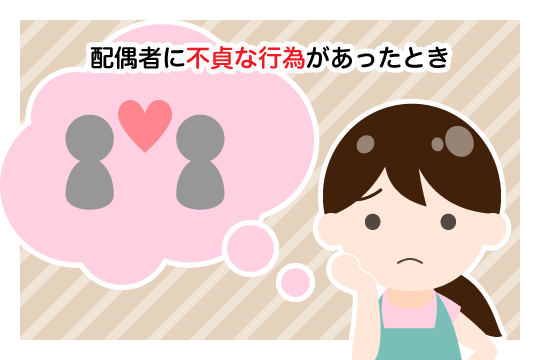
不貞行為とは、結婚している者が、貞操義務に反して配偶者以外の異性の人と肉体関係をもつことをいいます。
裁判で配偶者の不貞行為を認めて離婚するには、不貞行為の事実がわかる証拠が必要となります。
例えば、ラブホテルに出入りしている写真や動画、不貞相手と肉体関係があることがわかるメールやLINEのやりとりなどです。
ただし、不貞行為があったときに、すでに長期間にわたって別居しており夫婦関係が破綻していれば、不貞行為が離婚原因とはならない場合もあります。
そのほかにも不貞行為の事実から、数年の長い時間が経っていると、すでに夫婦関係は修復して解決できていると判断される場合もあります。
配偶者から悪意で遺棄されたとき

「悪意の遺棄」とは、夫婦は同居し、協力して扶助し合わなければならないという、民法に規定されている同居・協力・扶助義務に反する行為のことです。
具体的には、十分な収入があるのに生活費を家庭に入れない、正当な理由もなく別居するといった行為が、悪意の遺棄にあたる可能性があります。
悪意の遺棄にあたるかどうかは、行為の目的、期間、経緯などの事情を総合的に考慮して判断されます。こうした事情を踏まえて正当な理由があるといえない場合には、悪意の遺棄にあたると判断します。
悪意の遺棄の証拠となり得るものの例としては、次のようなものがあります。
- 正当な理由もなく家を出て行ったことがわかる置き手紙やメモ、メール
- 生活費を支払わなくなったことがわかる預貯金通帳の入金履歴、家計簿
配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
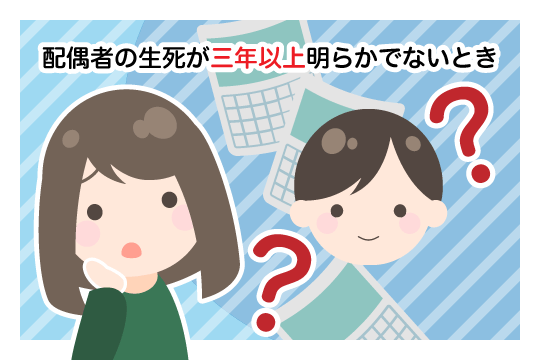
「配偶者の生死が3年以上明らかでない」というのは、配偶者と最後に連絡を取ってから3年以上、音信不通で生死不明の状態が続いていることを意味します。
なぜ3年以上の生死不明が法定離婚事由の一つにされているのかというと、配偶者が生死不明である場合には、生涯共同生活を送るという婚姻の目的を達成することはできないため、裁判での離婚請求を認める必要があるからです。
なお、3年以上の生死不明を理由に離婚が成立した後、配偶者が生きていたことが判明したとしても、確定した離婚判決は取消しにはならず、婚姻関係も復活しません。
配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき

「強度の精神病で回復の見込みがない」とは、夫婦生活を送っていくうえで必要な協力扶助義務を果たせないほどの重症な精神病を患っており、回復する見込みがない状態をいいます。回復の見込みについては、医師によって判断されます。
ただ、「強度の精神病で回復の見込みがない」という法定離婚事由に当てはまっていたとしても、裁判所はなかなか離婚を認めません。離婚を認めてしまうと、精神病を患っている者を見捨てるようなかたちになるおそれがあるからです。
離婚が認められるためには、相手が今後も治療や生活を問題なく続けていくための具体的な対策を考え、それが実現する見込みをつけることが重要なポイントになってきます。
その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

「婚姻を継続し難い重大な事由」とは、夫婦関係が破綻しており、夫婦関係の修復が著しく困難な状態にあることとされています。
判断要素としては、夫婦それぞれが婚姻を継続する意思を失っているという「主観的要素」と、夫婦関係を修復することが不可能である状態という「客観的要素」があり、裁判所は「婚姻を継続し難い重大な事由」に当てはまるか否かを個別の事情に応じて判断します。
法定離婚事由にある「婚姻を継続し難い重大な事由」として認められる可能性のあるケースとして具体的には次のようなものです。
- セックスレス
- 同性愛、性交不能、性的異常
- DV、モラハラ
- 別居
- 家庭内別居
- 金銭問題
- 配偶者の親族との不和
- 宗教
- 犯罪行為で服役
- 性格の不一致
- 家事や育児に非協力的
- 子供ができない
などです。次項からひとつずつ確認していきましょう。
セックスレス
性交渉を持つことは、夫婦が円満な婚姻生活を送っていくうえで重要な要素と考えられています。そのため、互いに健康体であるなど、性交渉に支障がない状態であるにもかかわらず、正当な理由なく長期間にわたって性交渉を拒否してセックスレスになり、婚姻関係の破綻に至った場合には、婚姻を継続し難い重大な事由があると認められる可能性があります。
セックスレスを理由とした離婚について、詳しくは下記の記事をご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
同性愛・性交不能・性的異常
同性愛者であることや、性交不能であることを隠して結婚した場合や性的異常によって、夫婦関係に亀裂が生じ、夫婦間の生活に悪影響を及ぼしている場合には、婚姻を継続し難い重大な事由であると認められる可能性があります。
なお、かつては同性愛者との不倫は「不貞行為」に該当しないと考えられてきましたが、近時、裁判所において、同性間での性的行為について「不貞行為」に該当すると判断したケースがありました。社会における性的マイノリティの捉え方の変化に対応して、裁判所の認定も変わってゆくことが予想されます。
上記に対し、病気や加齢などが理由で性交不能となった場合は、婚姻を継続し難い重大な事由とは認められないでしょう。
DV・モラハラ
相手からのDV(家庭内暴力)やモラハラ(侮辱・暴言)を受けている場合は、婚姻を継続し難い重大な事由になる可能性があります。
軽度のDVやモラハラであっても、日常的に長期間にわたって行われているケースでは、婚姻を継続し難い事由に該当する可能性があります。
一方で、たとえ一度のDVであったとしても、被害を受けた程度が重大であれば、離婚事由になり得るでしょう。
また、夫婦間だけではなく、子供に対してDVやモラハラを行った場合でも、離婚事由となる可能性もあります。
「DV加害者と離婚するためにできること」「モラハラ」については下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
別居
夫婦が長期間にわたって別居している場合は、婚姻を継続し難い重大な事由になる可能性があります。
夫婦が正当な理由もなく長期間の別居をしているということは、夫婦関係がすでに破綻していると判断できるからです。
「長期間の別居」とは、どれくらいなのかは、具体的に定められていません。
一般的には、3~5年程度を目安とされていますが、夫婦の結婚期間や別居期間の長さなど個別の事情を考慮して離婚を認めるかどうか判断します。別居期間が長ければ長いほど、離婚が認められやすいでしょう。
「離婚前の別居」については下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
家庭内別居
家庭内別居が、婚姻を継続し難い重大な事由になる可能性は低いでしょう。
家庭内別居は、同じ家に生活しているので、まわりから見ると夫婦関係が破綻しているかどうかわかりづらく、離婚事由となる可能性は低いのが実情です。
家庭内別居でも離婚を認められるためには、別々の部屋に過ごしており、一緒に食事しない、寝室も別々、家事・洗濯なども別々ということがわかる客観的証拠を揃えましょう。
「家庭内別居」については下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
金銭問題
一方配偶者の浪費癖や借金癖などの金銭問題で家計が苦しくなり、夫婦仲が冷めきっている場合には、婚姻を継続し難い重大な事由があると認められる可能性があります。
例えば、夫がギャンブルに依存して借金を繰り返し、生活費までギャンブルに使ってしまい家庭にお金を入れなかったり、妻が仕事も家事もせずに、借金をしてまで生活レベルに見合わない高価な買い物ばかりしたりしている場合には、当該事由があると認められやすいでしょう。
親族との不和
「配偶者の親族と仲が悪いから」という理由だけでは、離婚は認められにくいです。しかし、親族との不和を知りながら、配偶者が何の協力もせずに見て見ぬふりをしているなどの場合には、婚姻を継続し難い重大な事由があるとして、離婚が認められる可能性があります。
また、親族との不和でよくあるのが、嫁姑問題です。姑が嫌みを言ってきたり、無視したりするなどのモラハラ行為をしているケースもあるでしょう。姑のモラハラに何も言わずに妻を助けない、姑の味方をして一緒に嫌みを言ってくるといった状況にあるなら、離婚できる可能性があります。詳しくは、下記の記事をご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
宗教
宗教を信仰する自由は憲法で保障されており、夫婦間においても守られる必要がある自由です。そのため、配偶者が宗教を信仰しているから、夫婦で信仰している宗教が違うから、といった理由だけでは婚姻を継続し難い重大な事由があるとは認められません。
ただ、あまりに宗教活動にのめりこみ、育児や家事、仕事などに支障をきたし、家族に損害を与えているような場合もなかにはあります。このように、宗教活動によって婚姻生活がうまくいかなくなってしまった場合には、当該事由の存在が認められることがあります。
犯罪行為で服役
殺人等の重大犯罪で服役しているような場合を除き、一方配偶者が罪を犯し服役したからといって、直ちに婚姻を継続し難い重大な事由があるとは認められません。
しかし、配偶者に対する犯罪によって服役しているような場合や、犯罪を何度も繰り返し、家族の日常生活に困難を生じさせている場合には、当該事由があると認められる可能性があります。軽微な犯罪であっても同様です。
認められにくいケース (性格の不一致など)
性格の不一致
離婚理由で最も多いのが「性格の不一致」です。しかし、単に相手と性格が合わない、という理由だけでは、婚姻を継続し難い重大な事由と認められにくいでしょう。元々、生まれも育ちも違う環境の男女二人が、一緒に生活をすることになるのですから、性格や価値観などが違って当たり前です。
性格の不一致がきっかけで、長期間の別居をしていたり、夫婦関係を修復する気持ちが双方に完全になかったりする場合など、性格の不一致に加えて、他の原因もあって、夫婦関係が破綻している状態であれば、当該事由が認められる場合もあるでしょう。
「性格の不一致で離婚したい場合の対処法」について、下記ページに詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
家事・育児に非協力的
特に共働きの夫婦では、夫が家事・育児をしてくれないとよく問題になりますが、それだけでは婚姻を継続し難い重大な事由と認められにくいでしょう。
家事・育児を協力してくれないことがきっかけで夫婦喧嘩が繰り返されて別居に至り、夫婦関係が破綻している状態であれば、当該事由が認められる場合もあるでしょう。
子供ができない
子供ができない、という理由だけでは、婚姻を継続し難い重大な事由とはなりません。
しかし、子供ができないことが引き金となって言い争いが増えて、夫婦仲が悪化し、お互いに修復する気持ちがない状態となった場合には、夫婦関係が破綻しているとして、当該事由が認められる場合もあるでしょう。
また、健康上の理由で子供を作れない身体だと自覚しながら、隠して結婚した場合は当該事由として認められる可能性は高いでしょう。
不妊が原因でうつ病になってしまう方もいらっしゃいますが、そのような場合に離婚が認められるかなどについては、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います
離婚問題ご相談予約受付来所相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。
※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
お電話でのご相談受付
0120-979-164
24時間予約受付・年中無休・通話無料
メールでのご相談受付
メールで相談する離婚理由についてよくある質問
- Q:
うつ病は「強度の精神病」として離婚の理由になりますか?
- A:
-
配偶者がうつ病を患っていたとしても、法定離婚事由のひとつである「回復の見込みがない強度の精神病」に該当するとして、離婚が認められるのは難しいでしょう。
「強度の精神病」とは、具体的な病名でいうと、統合失調症、双極性障害などです。夫婦には、お互い助け合いながら結婚生活を送っていかなければならないという「相互扶助義務」があります。相互扶助義務が果たせないほどの重い精神病になり、かつ回復の見込みがないと医師に診断された場合に限り、「回復の見込みがない強度の精神病」に該当し、離婚が認められることになります。
よって、うつ病の状態・具合にもよりますが、「強度の精神病」として、離婚できる可能性は非常に難しいということになります。しかし、うつ病の配偶者からDVを受けている場合や、うつ病を発症したことをきっかけに長期間の別居をしている場合などは、「その他婚姻を継続し難い重大事由がある」として離婚が認められる場合もあるでしょう。
「うつ病は離婚の理由として認められるか」、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
- Q:
何年ぐらい別居をすれば、離婚理由になりますか?
- A:
何年間別居したからといって、自動的に離婚が成立するわけではありませんが、一応の目安はあります。過去の裁判例をみると、3~5年程度を目安に離婚を認めていると思われます。ただ、あくまでも目安なので、参考程度にとどめておきましょう。
なお、有責配偶者(離婚の主な原因を作った配偶者)からの離婚請求は基本的に認められませんが、例外的に認められるケースもあります。判例(最高裁 昭和62年9月2日大法廷判決)では、①相当長期の別居が続いており、②未成熟子がおらず、③離婚によって相手方配偶者が精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状況に置かれないことを、有責配偶者からの離婚請求を認めるための要件としています。このうちの「①相当長期の別居」について、一般的な目安は7~10年程度といわれています。
- Q:
働けるのに夫が働いてくれない場合、離婚理由になりますか?
- A:
働けるのに夫が働いてくれない場合は、離婚が認められる可能性は高いでしょう。
例えば、「病気やケガで働けない」、「夫婦で話し合って専業主夫となった」など正当な理由がないのであれば、健康な身体なのに無職である証拠や家庭にお金を入れていない証拠などを集めておきましょう。認められれば、法定離婚事由である「悪意で遺棄されたとき」、もしくは「その他婚姻を継続し難い重大な理由がある」に当てはまり、離婚が認められる可能性はあります。
- Q:
理由がない場合でも離婚はできますか?
- A:
離婚理由がなくても、協議離婚と離婚調停の方法であれば、相手が離婚に合意すれば離婚できます。
相手が離婚を拒んでおり、協議離婚、離婚調停を経ても話し合いで解決できなかった場合は、離婚裁判を提起することになりますが、離婚裁判では、離婚理由がなければ、裁判官が離婚を認めるのは極めて難しいでしょう。
離婚には理由が必要となる場合があります。離婚に関するお悩みは弁護士にご相談ください
民法770条1項には、裁判で離婚するために必要な離婚原因が定められています。離婚裁判を行うことになったら、ここに規定されている離婚原因(法定離婚事由)があるかどうかが重要なポイントになってきます。
「これって法定離婚事由になるの?」「裁判で法定離婚事由を主張・立証していくのに不安がある…」などのお悩みを抱えている方は、ぜひ弁護士の力を頼ってみてください。弁護士なら、法的知識に基づいて適切に判断し、お一人おひとりの状況に合わせたアドバイスができます。また、あなたの代わりに、裁判官に対して論理的な主張や立証をしていくことも可能です。
離婚はもちろん、内縁関係や婚約破棄といった男女のトラブルに関するお悩みについても、弁護士にお任せください。最善の解決を目指してサポートさせていただきます。
まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

- 監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
- 保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)















